教区報
主教コラム
「昨日も今日も、また」2025年9月
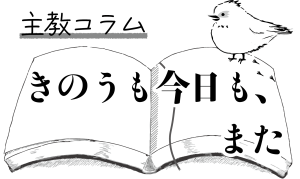
4月の大阪教区主教按手式に続き、7月5日九州教区主教按手式ならびに九州教区主教就任式が挙行されて、マルコ柴本孝夫新主教が誕生しました。私が柴本主教で一番に思い浮かぶのは支援車両です。
2011年3月11日東日本大震災後に日本聖公会が立ち上げた被災者支援「いっしょに歩こう!プロジェクト」では、活動のため複数台の車両を必要とし、沖縄教区からは新車同然の10人乗りワゴン車が提供されました。ワゴン車は沖縄から九州に輸送後、当時の柴本司祭と九州教区信徒の山本尚生さんが陸路丸々2日間掛け本州縦断、仙台まで運転して来てくださったのです!これだけでも凄いお働きでした。
車のボディには、聖公会の日本宣教開始とされている米国聖公会リギンズ宣教師とウイリアムス主教が長崎に上陸した1859年より13年前の1846年に、イギリスの琉球伝道団から「ベッテルハイム」という医師の宣教師が那覇に来て、迫害の中で8年間伝道していたその人の名が印字されていました。「沖縄」のナンバープレートの車に、スタッフは「うちなんちゃー」の愛称を付けて愛用しました。
緊急救援物資を北は釜石から南は小名浜まで運び、被災された方々をお乗せしてのお茶会や買い物ツアーにお出かけをし、全国から来たボランティアたちの輸送や訪問者の送迎など、13年間多くの場面で大活躍した車両でした。
昨年の能登半島地震後うちなんちゃー号は京都教区災害対策室に移譲され「京都」ナンバーで使用されています。私は京都教区主教館前に駐車しているその車を目撃し、感無量でした。柴本主教さんたちの行為は、こうして次から次へとバトンタッチされて、奉仕の継承がなされているのです。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、私は日本聖公会の宣教の歴史と継承、全体性と一体性、教区間協働の象徴としてのうちなんちゃー号に希望の光を感じます。
(教区主教)
