教区報
主教コラム - 昨日も今日も、またの記事
「昨日も今日も、また」2024年4月
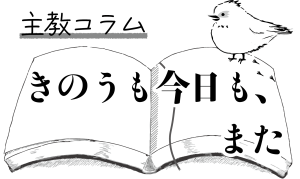
主のご復活を慶びお祝い申し上げます。
2月6~8日、主教会が沖縄教区名護聖ヨハネ教会で開かれました。本州最北端の青森から遥か海を越えて南国那覇空港に降り立ちますと、空気が熱くて汗がにじみ出てきました。主教会
の2日目午後、ハンセン病国立療養所沖縄愛楽園を訪問し、ガイドを受けて資料展示室を見学、上原榮正主教の車で園内を案内していただきました。現在入所者は95名で平均年齢86歳だそうです。その後夕の礼拝前まで、祈りの家教会で信徒さんたちと懇談の時間を持ち楽しく歓談しました。
青森市にある国立療養所松丘保養園にお暮らしの松丘聖ミカエル教会信徒が、昨年12月と本年1月、続けざまに天に召されました。お二人とも老衰で、自室にて安らかに天の主の御許に旅立ちました。葬送式には動ける殆どの入所者と職員の方々が施設のホールに集われて見送られ、しみじみとした平安を感じました。コロナ禍で保養園は厳しい入構制限がかかり、私は4年間入室出来ずにおりましたが、お二人にはどこかでお会いしてたかもしれません。
30年程前、教区教役者研修会で当時特任聖職執事ヨハネ福島政美さんや信徒たちと礼拝をして懇親会を持ちましたから、その席にお二人がいらしたはずです。去年9月、藤崎陸安さんが多
摩全生園にて80歳でご逝去されました。私と同じ秋田県出身で、20年程前秋田聖救主教会の大斎節講演会で講師だったのを昨日のように思い出しました。ミカエル教会信徒は、とうとうお一人になってしまいました。現在入所者は34名で平均年齢89歳です。
神戸教区から出向され、3年間お働きくださったテモテ遠藤洋介司祭のご奉仕に感謝し、新任地での更なるご活躍を祈念いたします。主の平和
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2024年5月
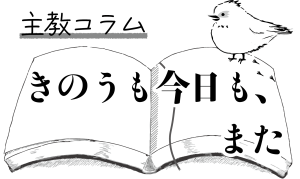
洗礼堅信式が行われますと、私たちは有り余るほどのお恵みを賜っている幸福感を味わいます。3月17日、山形聖ペテロ教会で米沢聖ヨハネ教会合同洗礼堅信式がありました。山形の方は遠藤洋介司祭から洗礼を授けられ、続いて米沢の方とお二人で堅信を受領されました。洗礼名は各々の教会名にちなんでペテロと施洗者ヨハネです。山形に籍を置かれる方は今年、高校を卒業して大学に入学されます。米沢に籍を置かれる方は、少年期に他教会で洗礼を受けていましたが、母親のことがあって聖ヨハネ教会の礼拝に通われて信徒の交わりをされての堅信でした。老いも若きも共々に等しく神さまの愛を賜るさまに、麗しさを覚えた一日となり深く感謝いたしました。
昨年のクリスマスには、青森聖アンデレ教会で親子3人の洗礼堅信式がありました。3歳と5歳のお子さん2人は聖公会の幼稚園の園児さんです。子どもたちにとって洗礼盤が高いので、幼稚園の大型積み木を重ねて階段にしました。式が始まった頃はもじもじしてお母さんに纏わり付いていましたが、2人ともいざ自分の番になるとその階段を真剣に2段登り、手を合わせ神妙な面持ちで受洗しました。その可愛らしさに誰もが心打たれておりました。お母さんは洗礼後両脇に子たちをしたがえての堅信式となりました。その光景もまたいじらしく、聖堂内に温かな笑顔と遠慮がちな笑い声が起きました。微笑ましい一時でした。
受洗者堅信受領者だけでなく教父母たちも、居合わせた人たちも、どなたもが神さまに愛される子どもであり、教会はこの愛する子たちのコ
ミュニティです。だれも彼もが神の子であるならば、そのコミュニティは神の家族です。神の家族の一員になられた兄弟姉妹たちを心から大歓迎し迎え入れ、声かけあい共に信仰を深め成長でるよう、祈り合ってまいりましょう。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2024年6月
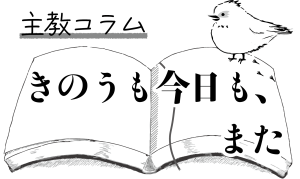
4月人事異動で青森聖アンデレ教会管理牧師を辞し、仙台聖フランシス教会管理牧師に着任しました。青森では4年という短期間の牧会でし。2020年4月、8年勤務した仙台基督教会から移った時は定年退職まで残り8年でしたから、きっと最後の異動だろうと思いこの地に骨を埋める覚悟でした。ウイリアムス神学館在学中に教授たちや先輩の神学生たちから「主教に派遣された地で死ぬ覚悟を持て!」と意気込みを伝授されたもので、素直な私はどんな時もどこであろうとも、遣わされた土地で殉教したら本望と心得てきました。
引越当日4月8日は快晴、4年前青森に入った日は冷たい雨だったのにと述懐しました。合見積の結果発注した引越業者は、青森の幼稚園がいつもお世話になっており、ご厚意による員数と台数で2時間半ほどで荷積み完了、恵まれて感謝でした。夕刻には仙台入りができ、疲労も少なく
有り難いことでした。
翌4月9日は聖クリストファ幼稚園始園日ということもあり搬入は午後になりましたが、朝から雨で止みません。寒さが加わった14時30分頃から開始するも、荷はすべて梱包され、他は段ボールですから物が濡れません。これもまた有り難いことです。牧師館はややコンパクトサイズで箪笥や大型家具を階段では2階に上げられません。2階の窓を外して吊り上げ方式となり、作業員全員が上下二手に分かれて「せーの」と掛け声揃えて力を合わせ、「うんとこしょ、どっこいしょ」と何とかすべてが各部屋に納まりました。この作業に取り掛かる時には雨があがっていたのは誠に幸いなことでした。完了時刻19時57分、私たちは玄関前に円陣を組んで、有り難うとおめでとう、お疲れ様と声掛け拍手して解散したのでした。
青森でもフランシスでも信徒たちがお顔を見せてくださり心強く本当に感謝でした。「雨降って地固まる」私の引越物語です。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2024年7月
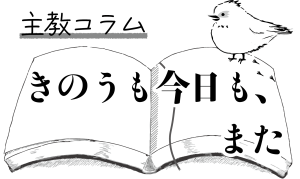
5月25日(土)午前11時から、大田教区設立59周年記念と主教座聖堂礼拝堂聖別式が執り行われ、私は常置委員長赤坂有司さんと李贊熙司祭と3人で参列しました。ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー供給と資材高騰の煽りで工期が遅れ、建設工程の98%の段階です。3階の聖堂は桁外れに高く、天を見上げる感じの空間です。困難な時代に大聖堂を建立奉献する一大事業を成し遂げられたことに対して、私は心からの敬意と称賛を贈りました。
式の最後に設計監理者と施工者への感謝盾贈呈式と、タンザニア聖公会タンガ教区と大田教区の姉妹教区締結調印式が行われました。大田教区テトス主教は司祭時代から水に困っていたタンザニア聖公会に援助しており、この度マインボ首座主教と正式調印してその支援を教区レベルに格上げして充実されるのです。
その後で、私は東北教区からお祝いの「会津絵ろうそく」をお渡しして「信仰の火」「宣教の炎」を灯し続けてくださいと挨拶しました。かねてより友好関係があったマレーシア聖公会のヤコブ司祭からも大田教区のテトス主教にプレゼントがありました。今年大田教区40名の教役者たちの半分が、マレーシアで研修を開く計画だと聞かされて、その国際性の意識の高さに学ぶところ大でした。
翌日の主日聖餐式で説教しましたが、逆の場合でも私も同様にテトス主教に説教を依頼することでしょう。そう遠くない時期にご訪問していただきますようにとラブコールしましたら、会場で賛意の笑い声が広がったのにはウキウキさせられました。
主教同士の行き来だけでなく、信徒や教役者の相互訪問が活発化されて両教区の主にある交流が深められ、宣教が拡大されますようにと願うものです。そのためにお互いにもっともっと多く出会い、理解し合い、祈り合うパートナーの絆を太くしたいと願いました。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2024年10月
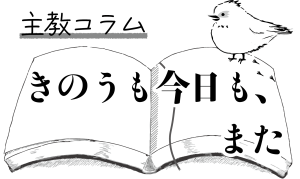
USPG(United Society Partners in the Gospel)の主催するリーダーシップトレーニングが、7月3日から23日まで栃木県那須塩原市にあるアジア学院を会場にして行われ、世界中から聖公会の青年たち9名が参加しました。
国別では、イギリス、パプアニューギニア、バングラデシュ、ブラジル、パレスチナ、そして日本でした。
プログラム中頃の7月12日に、私はアジア学院を訪問し参加者たちに東日本大震災についてお話ししました。
大地震と巨大津波と東京電力福島第一原子力発電所爆発事故による放射能被害、避難者のご苦労、
13年4カ月後の現況等を、スライドと、最新の福島県地図と東北地図を広げながら、想像できているかを随時確認しながら説明しました。
青年たちは熱心に耳を傾けて、時に目頭を熱くし、時に暗い顔をして痛みや怒り、悲しみ、口惜しさの感情を表していました。
彼らの感受性に接し、私は不思議と救われた思いで一筋の光を見ていました。
翌13日は朝から中型バスに同乗しての福島フィールドワークでした。福島県富岡町夜の森公園を経由して国道6号線に入り北上、車中から立入禁止の看板や倒れたままの家屋、大熊町で原発内の大型クレーンを目にしました。
初めて訪れる震災遺構浪江町立請戸小学校に立ち寄り、英語のガイド書を読みながら、さび付いた建物内を約1時間見学しました。日頃の避難訓練や津波に対する危機意識の重要性、また逃げている人同士の助け合いが奇跡を生んだ事実を知って、衝撃と感動を受けたと話す青年がいました。
最後に、新地町の祈りの庭で磯山聖ヨハネ教会信徒から大震災後の教会再建の苦労話を聞き聖餐式を献げ、その後磯山聖ヨハネ教会でアイスをほおばり信徒との語らいを持ちました。
この貴重な体験を今後の信仰に肉付けして、命の尊さを忘れずにと願ったことでした。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2024年12月
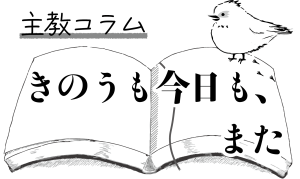
今年は韓国に3回も行かせていただき、なんという恵みでしょう。5月大田主教座聖堂聖別式、9月ソウル教区主教按手式、10月日韓聖公会宣教協働40周年記念大会で済州島を訪ねたわけです。大会には日本聖公会から45名、大韓聖公会から32名、プラスACC総主事とカンタベリー大主教主席補佐官らの特別参加があって総勢80名が集まり、3泊4日のプログラムで行われました。東北からは青年2名と、李贊熙司祭です。1人の青年はハングルが流暢で、青年たちとのおしゃべりを楽しんで快活だったことに、未来への希望を感じました。
大会テーマは「和解」で、2日目は終日日韓の現場からの声を聴き合い、分かち合いました。私は「自然との和解」
の部で、原発のない世界を求めている活動報告をさせてもらい、発題後共感する人たちに握手を求められ感激でした。
参加者たちは2度オンラインで事前学習をして大会に臨んでいます。それがとても役立ちました。日韓宣教協働の
歴史と済州島の2つの歴史を学んだのです。1945年8月15日以降、アメリカ軍事政府から約5年間、済州島民は虐殺と処刑の迫害を受けた歴史を私は初めて知りました。「4・3事件」と呼ばれています。3日は済州4・3平和公園に出かけ犠牲者追悼礼拝を献げ祈り、平和記念館を見学し、戦跡フィールドワークしました。私は沖縄が重なってきて、たいへん心痛み気持ちが重くなりました。その後、昨年礼拝堂聖別式が行われた済州友情教会に隣接して建てられた「済州日韓友情の家」の祝福式が、両首座主教の朴東信(パクドンシン)主教と上原榮正主教の共同司式により挙行されたのは目に見える和解と友好のしるしです。
友情の家は宿泊施設で日本聖公会の方には2025年中無料で貸し出されます。和解と平和、風と聖霊の島を旅する際はご利用できます。申し込みは長谷川まで。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2025年2月
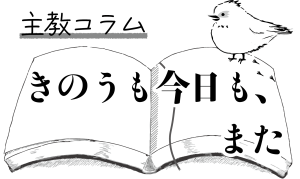
昨年11月17日、仙台聖フランシス教会での主日聖餐式で「誕生感謝の祈り」を執り行いました。仙台市にお住いの札幌聖ミカエル教会信徒ご夫妻に、10月初めての赤ちゃんが誕生しました。札幌から父親のご両親も
駆けつけ家族揃って感謝を献げられました。式の間赤ちゃんの元気よい泣き声が聖堂内狭しと響き渡って、会衆は清々しく幸せな気持ちに包まれました。神様からの賜物の大きさを想い、赤子の成長と家庭の平安のため、また3人の親子に豊かな祝福をお祈りいたしました。
12月、青森聖アンデレ教会と弘前昇天教会の2教会と、聖マリア幼稚園、聖アルバン幼稚園、聖ヤコブ幼稚園そして明星幼稚園の4園で礼拝とクリスマス会を持ちました。少々あった疲労よりもお恵みのラッシュで神的な栄養をたっぷり頂いて心は健康です。
降誕日、弘前での聖餐式に自分の教会で礼拝ができなかった青森の信徒たちが勢い立ってレンタカーに乗り、11名が出席してさながら合同礼拝でした。祝会は昇天教会の皆さんが豪勢なオードブルを用意されて歓談に花が咲き、予期せぬ温かな信徒の交わりが展開されて感謝な一日でした。
今冬の青森は50年で3度目の記録的な大雪で、12月に積雪1m超えは滅多にない現象です。私が青森聖アンデレ教会に異動した2020年の冬がその1回で、赴任1年目に豪雪の大歓迎を受け、雪国の洗礼を受けたのを思い出しました。北の国では当たり前のことで特別驚くものではないですが、除排雪や寒さを忍耐し暮らすのは大変です。そういう環境に慣れ親しみ、何かで楽しまなければやはり辛いだけになってしまいます。
暗くホワイトな午後に園児さんたちが演じる聖劇は、神様の愛のぬくもりとキリストの光を強烈に感じさせるものでした。子どもたち、保護者さんたちと先生方に神様の祝福がいっぱいありますようにお祈りいたしました。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2025年4月
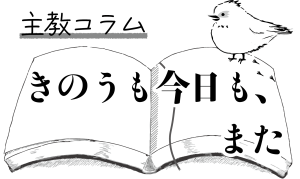
1月、2月も管理教会がある青森と弘前を往復しましたが、今年の大雪にはひどく影響を受け、悩まされました。奥羽本線運転見合わせが何度もあって、1月4日は八戸の聖餐式後弘前に行くために駅に向かうと、無理との
こと。思案していると仙台行新幹線にキャンセルが出たというので、予定を変更し弘前は諦めました。信徒もこの大雪では交通も安全も脅かされると教会委員で相談の上、礼拝を休止としました。
2月5日から7日は西日本が寒波と大雪の中で、熊本を会場に主教会。帰路予約していた伊丹空港経由仙台着を断念し羽田空港に変更、東京駅から新幹線で帰宅。
2月19日、前日チーム北国会議の札幌から青森空港への飛行が怪しく、急遽札幌から新函館北斗を経由し新幹線で青森へ。翌日、奥羽本線運転見合わせで鉄道では弘前に行けず。スマホ検索して新ルートを発見、青森空港経由でリムジンバスを乗り継いで弘前に到着。
20日帰路、運転再開で電車に乗るも北常盤駅でポイントを切替できず約2時間停車。代行バスで新青森駅へ。
3時間遅れで帰宅。 足止めを食らった時、目的地に辿り着くのに頭を柔軟にします。計画や予定に縛られず、変更を躊躇しない、それが打開の秘訣かと貴重な体験を積みました。ラインホルド・ニーバーの祈り「変えられる
ものを変える勇気」が少し解りました、感謝です。
有我忠幸聖職候補生が聖公会神学院の「特任聖職・特別オンライン講座」1年間の受講を終了しました。次のステップに進みます。4月からは国分敬子さん(郡山)と白鳥五大さん(青森)のお二人が「信徒の奉仕・召命コースオンライン講座」を受講します。諸経費は研学資金で援助します。二人とも信徒奉事者です。
東北教区の信徒奉事者47人は日本聖公会で3番目に多い人数。信徒の奉仕の働きの広がりを願う中、今まさにチームミニストリーを推進しようとしている我が東北教区に弾みが付くと、私はとても喜んでいます。
(教区主教)
