教区報
主教コラム - 礼拝堂探検隊の記事
礼拝堂探検隊 第21回「チャリス・パテン」
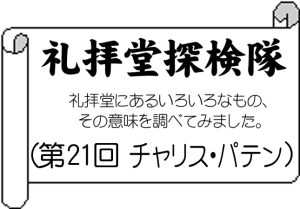 今回は聖餐式の時に聖別されたぶどう酒を入れるチャリスと、パン(ウエファース)を入れるパテンです。金または銀で作られていますが、それは酸による腐食を防ぐためだそうです。
今回は聖餐式の時に聖別されたぶどう酒を入れるチャリスと、パン(ウエファース)を入れるパテンです。金または銀で作られていますが、それは酸による腐食を防ぐためだそうです。
初期の時代のパテン(paten 聖皿)は、会衆から献げられた大きなパンを受けるためにかなりの大きさだったようです。しかし中世中期になりますと、パン(聖体)が種なしの薄いものになった関係で、パテンも小さくなったようです。
初期の時代のチャリス(Chalice 聖杯) はガラス製が一般的でしたが、ほかの素材(木製など)を使うこともありました。チャリスの最も古い形は、カタコンベに描かれているもので、二つの取っ手がついた、柄(ステム)のないボウル状だったそうです。
4世紀に入ると金製や銀製が一般的になり、それに宝石などを嵌めたものも作られました。もっとも9世紀頃までは陶磁器や木製のものもあったそうです。映画の「インディー・ジョーンズ 最後の聖戦」で登場した聖杯も木製でしたが、宗教改革者ツヴィングリも木製のものを使ったそうです。現在のような形になったのは14世紀だそうです。
 最後の晩餐の記事のように、聖別されたぶどう酒は一つの杯より飲むのが正当とされています。なぜなら主イエスは「皆、この杯から飲みなさい」(マタイ26:27)と言われたからです。プロテスタント教会で個人用のカップを用いる所がありますが、主として衛生的見地から19世紀に米国で始められたものです。しかしこれでは「分ち合う」という意味を弱めてしまうと言う批判もあります。
最後の晩餐の記事のように、聖別されたぶどう酒は一つの杯より飲むのが正当とされています。なぜなら主イエスは「皆、この杯から飲みなさい」(マタイ26:27)と言われたからです。プロテスタント教会で個人用のカップを用いる所がありますが、主として衛生的見地から19世紀に米国で始められたものです。しかしこれでは「分ち合う」という意味を弱めてしまうと言う批判もあります。
(教区主教)
礼拝堂探検隊 第6回「聖堂ー②」
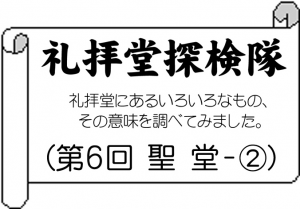

日本聖公会の多くの聖堂は、英国の典型的な大聖堂を縮小し、簡略化した構造をしているものが多いようです。
このような大聖堂は、上から見ると十字架型をしているものが多いのですが、東北教区の教会で明らかに十字架型をしているのは、山形聖ペテロ教会の聖堂です。
この十字架の横木の部分をトランセプト transept(翼廊)と呼び、縦木の会衆席の部分をネイブ nave(身廊)と呼びます。山形聖ペテロ教会では、右側のトランセプトにオルガンを置いています。翼廊の部分を小聖堂として用いている教会もあります。
 ネイブ naveというのはラテン語のナヴィス(navis・船)からきた言葉で、教会をこの世の嵐の中を漕ぎ渡る船にたとえています。マルコ4・35に嵐の中、腕枕をして眠っておられたイエス様の話がありますが、このことを思い起こさせます。つまり、会衆席は「救いの箱舟・安心して居ることのできる場所」を象徴しているとも言えるでしょう。
ネイブ naveというのはラテン語のナヴィス(navis・船)からきた言葉で、教会をこの世の嵐の中を漕ぎ渡る船にたとえています。マルコ4・35に嵐の中、腕枕をして眠っておられたイエス様の話がありますが、このことを思い起こさせます。つまり、会衆席は「救いの箱舟・安心して居ることのできる場所」を象徴しているとも言えるでしょう。
左の写真は弘前昇天教会のネイブから祭壇方向を見たものですが、上下逆にしてみてみると、天井部分がなんとなく古代船(ローマ帝国時代の船)の船底構造に見えませんか。
教区主教
礼拝堂探検隊 第22回「クリーデンス・テーブル」
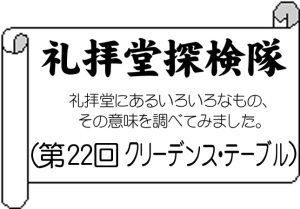
祭壇の左側(東面の時は右側)に置いてある小さなテーブルのことを「クリーデンス・テーブル(credence table)」と呼びます。
教会では、聖餐式に用いるパン・ぶどう酒などを用意しておくテーブルのことを指しますが、クリーデンスという英語は、「信用・信頼」という意味で、ラテン語のクレド(credo 私は信じます)が語源だそうです。もともとは味見や試食のための食物を置いたサイドテーブルを指す言葉だったようです。
 さて、このテーブルの上に置かれるパン(信徒用のウェファース)を入れる容器を「ブレッド・ボックス(bread box)」と呼び、読んで字のごとく「パン箱」です。またぶどう酒と水を入れる容器のことを「クルエット(cruet)」と呼びますが、これも単なる「小さな水差し」という意味です。ちなみにブレッド・ボックスの右側にあるのは、ラバボ・タオル(lavabo towel)とラバボ・ボール(lavabo bowl)です。ラバボとは「洗手」という意味です。
さて、このテーブルの上に置かれるパン(信徒用のウェファース)を入れる容器を「ブレッド・ボックス(bread box)」と呼び、読んで字のごとく「パン箱」です。またぶどう酒と水を入れる容器のことを「クルエット(cruet)」と呼びますが、これも単なる「小さな水差し」という意味です。ちなみにブレッド・ボックスの右側にあるのは、ラバボ・タオル(lavabo towel)とラバボ・ボール(lavabo bowl)です。ラバボとは「洗手」という意味です。
つまり、クリーデンス・テーブルも含めて、その上に置かれる各々の容器は特別なものではなく、ごく一般的・日常的なものであることが分かります。
ですから大切なことは、それらの容器に入れられたもの、つまりパンとぶどう酒と水が献げられ、感謝聖別の祈り・聖霊を求める祈りのうちに、キリストの御体と御血とされ、私たちを養ってくださるということではないでしょうか。また私たちの日常性が、祈りと聖霊の働きを通して聖なるものとされるということでもあると思います。
その意味で、それらを用意する机が「クリーデンス(私は信じます)テーブル」と呼ばれるのは、奥深い意味があるように思いますが、いかがでしょうか。
(教区主教)
