教区報
主教コラム - 欅並木からの記事
欅並木から 第14回「韓国との交流、協働のこと」
李贊煕司祭がご家族と共に、日本、東北教区に来られたのが2009年11月、それから東北教区での働きが始まりました。大韓聖公会と日本聖公会の間で交わされている宣教協働者派遣の協定によって李司祭はこの11月で2期6年を終えられますが、さらに3年の延長の契約を交わすことになっています。李司祭の健康と働き、またご家族のためお祈りし、ますます多くの教区の皆様との良い交わりが出来ますよう願っています。
一方、東北教区と大田教区の交流、宣教協働は2005年から始まり、現在10年目となりました。1期3年の3期9年が過ぎ、昨年教区会から新たな5年間の交流延長が始まっています。
東北教区の長い歴史の中で、ルイジアナをはじめ、いわゆるアメリカ、ヨーロッパのキリスト教には馴染みがあっても、アジアのキリスト教、韓国との交流はほとんどなかったのではないでしょうか?
それでも皆様が李司祭との交わり、韓国との交わりを自然に喜んで受け入れてくださったことは素晴らしいと感じています。
わたし自身、聖公会の司祭の家庭に生まれ育ちましたが、目はいつも「欧米」を向いていたと思います。神学生になって初めて、韓国との出会いがありました。日韓の歴史のこと、在日韓国朝鮮人の人たちの日本社会での労苦のこと、それらを知るにつれ、また最初は緊張感を持ちながらも韓国の友人が出来るにつれ、わたし自身が「自分が日本人である」ことを自覚し、いわば「自分は何者なのか」という問いに向き合うためには、どうしても韓国が必要だと思うようになったのです。政治的には難しい状況が続いていますが、そういう中でも絆を強めていく日韓聖公会の交わり。どうぞこれからも積極的な関心を持っていていただきたいと願います。
(教区主教)
あけぼの 2015年11月号
欅並木から 第15回「野村潔司祭への感謝」
9月10日に、中部教区司祭、テモテ野村潔師が逝去されました。63歳という若さでした。東北教区に奉職された野村義雄司祭のお孫さんですし、秋田の教会にご縁があります。長く中部教区の司祭として、とくに名古屋学生青年センター等、教会の社会宣教の現場で、多くの人たち、とくに若い人たちに大きな影響を与えながら働き続けられました。
東日本大震災発生の1週間後、名古屋から新潟、山形を経由して管区のスタッフも共に仙台に駆けつけてくださった中に、もちろん野村司祭の姿がありました。それ以降、「いっしょに歩こう!プロジェクト」の設立メンバーとして、2年間、本当にしばしば仙台に通い、プロジェクトの屋台骨であり続けたと言って過言ではありません。非常にラディカルな社会活動家的な顔、社会的な弱者に対する徹底した共感の姿勢と共に、生ぬるい面も多い教会、とくに東北教区の現実に対しても理解を示しつつ一緒に歩いてくださったと思います。「聖公会というのは、周りから、『まだそんなことやってるの?』と言われるくらいに、急に目覚ましいことは出来なくても、しつこくやり続ける教会なんだよ」と、プロジェクトの初期に言われていた言葉は、震災後の現在の東北教区に対して、今でも意味深い言葉だと思います。2年間のプロジェクトの後、日本聖公会の「原発と放射能に関する特別問題プロジェクト」の長となられましたが、その頃から体調が思わしくないような話も聞いていました。
 実は2003年に行われた東北教区主教選挙で、候補のお一人としてお名前が挙がっていたことを知っています。野村司祭が東北教区主教だったら、ずいぶん教区の姿勢や雰囲気も変わったのではないかと、時々思います。感謝と共に改めてその姿勢から学ぶ必要があると思うのです。
実は2003年に行われた東北教区主教選挙で、候補のお一人としてお名前が挙がっていたことを知っています。野村司祭が東北教区主教だったら、ずいぶん教区の姿勢や雰囲気も変わったのではないかと、時々思います。感謝と共に改めてその姿勢から学ぶ必要があると思うのです。
(教区主教)
あけぼの 2015年12月号
写真:東日本大震災直後、支援にかけつけてくださった野村司祭(右端・山形聖ペテロ教会にて)
欅並木から 第16回「声のこと―『み言葉の礼拝』の司式に寄せて―」
日本聖公会として『み言葉の礼拝』が作成され、刊行されてから数年が経ちました。司祭が不在の場合の日曜日の礼拝のためとなっており、全国の教区でかなり幅広く用いられているようです。従来の「朝の礼拝」でもよいのですが、『み言葉の礼拝』は聖餐式の場合と同じ聖書日課―旧約、使徒書、福音書―を読み、また代祷の形式も聖餐式と基本的に共通しています。つまり聖書朗読と代祷という、聖餐以外の礼拝の大切な部分を強調しているものと言えます。「朝の礼拝」ももちろん聖公会の宝ですが、日々の「聖務日課」として基本的には主日の礼拝とは異なる意図を持っていると言えます。
一信徒の方の年賀状に、『み言葉の礼拝』の司式者のための研修をよろしくとあり、申し訳なく思いました。努力したいと思います。
『み言葉の礼拝』でも他の礼拝の場合でも、司式者として大事なことは何かと言われれば・・・もちろんいろいろ大切なのでしょうが、わたしは「声」とお答えすると思います。司式する声です。しかし決して誤解していただきたくないのは、ただアナウンサーのように正確にきれいな声で、とか立派な声で司式してくださいと申し上げたいのではないということです。ほとんど「気持ちの問題」と言ってよいかと思います。
 そこに集まっている人たちといっしょに祈ろう、多くの場合会衆は小人数でしょうが、喜んで礼拝しよう、お互いに礼拝を通して神さまに感謝と賛美を捧げ、信徒同士も力づけあおう、それが一番大切な心なのだと思います。その結果としてボソボソというよりは多少声にも力をこめたり、またそのためには姿勢もうつむいて、というよりは胸を張ったり。新しい一年、少しでも多くの方と顔を合わせて研修の機会が持てたら幸いです。
そこに集まっている人たちといっしょに祈ろう、多くの場合会衆は小人数でしょうが、喜んで礼拝しよう、お互いに礼拝を通して神さまに感謝と賛美を捧げ、信徒同士も力づけあおう、それが一番大切な心なのだと思います。その結果としてボソボソというよりは多少声にも力をこめたり、またそのためには姿勢もうつむいて、というよりは胸を張ったり。新しい一年、少しでも多くの方と顔を合わせて研修の機会が持てたら幸いです。
(教区主教)
あけぼの 2016年3月号
欅並木から 第6回「沖縄の旅・主教会」
 6月24日(火)から27日(金)まで、定期主教会が沖縄で開催されました。定期主教会は基本的に年3回で、一回は東京のナザレ修女会で開催し、あとは各教区を順番に回ります。その教区の宣教課題があるところ、是非紹介したい働き等を訪問する良い機会になっています。最も通常2泊3日の日程の大半は会議室に缶詰で、数十に及ぶ報告や協議事項があり、大変疲れる会合ですが、同時に教区主教という同労者がお互いの状況を知合い、また日本聖公会としての一致と方向性を確認する貴重な機会ともなっています。
6月24日(火)から27日(金)まで、定期主教会が沖縄で開催されました。定期主教会は基本的に年3回で、一回は東京のナザレ修女会で開催し、あとは各教区を順番に回ります。その教区の宣教課題があるところ、是非紹介したい働き等を訪問する良い機会になっています。最も通常2泊3日の日程の大半は会議室に缶詰で、数十に及ぶ報告や協議事項があり、大変疲れる会合ですが、同時に教区主教という同労者がお互いの状況を知合い、また日本聖公会としての一致と方向性を確認する貴重な機会ともなっています。
とくに今回は沖縄の直面している状況を学ぶため、日程も3泊4日1日長くして、その1日は沖縄の戦跡、基地のフィールドワークに充てられました。宿泊した那覇おもろまちのホテル自体が高台にあり、そこは沖縄の命運を分けた激戦の丘であったとのこと。普天間基地の見学(もちろん外から)オスプレーも見えました。基地のために埋め立てが進められようとしている辺野古では全員小舟に乗って海に出て、その状況の説明を受けました。本当に戦い続けている島という印象を強くしました。
沖縄でのもう一つの話題は、沖縄教区が現主教を総会で与えられるまで、主教選出に難渋し、教役者数、信徒数も少ない中で教区としての将来をどう考えるのかということでした。しかし教役者や信徒数の減少・高齢化は沖縄に限らず、全国的な問題です。沖縄教区は確かに小さな教区でしょうが、しかし非常に大きな課題に取り組みながら、独自の歴史と文化をもって大変生き生きとしていると感じました。教区でも教会でもそうなのでしょう。規模の大小の問題よりも、自分たちの現実に真剣に向き合う中から、信仰的な力も与えられてくるのだと感じさせられた沖縄の主教会、旅でした。
欅並木から 第17回「ナザレの家に想う」
 仙台市青葉区台原にある「ナザレの家」は、太平洋戦争後、戦前の「婦人伝道師および幼稚園教師の養成機関」であった青葉女学院復興の希望のもと、現在同区内小松島にある青葉静修館となる建物、幼稚園、さらには教会、牧師館という総合的な視野の中で建築され、とくに1956年に中村信蔵主教の招聘によって来日した米国・変容貌修女会のシスター方が居住して幼稚園への奉仕活動の拠点となった、意義深い歴史を持つものでした。
仙台市青葉区台原にある「ナザレの家」は、太平洋戦争後、戦前の「婦人伝道師および幼稚園教師の養成機関」であった青葉女学院復興の希望のもと、現在同区内小松島にある青葉静修館となる建物、幼稚園、さらには教会、牧師館という総合的な視野の中で建築され、とくに1956年に中村信蔵主教の招聘によって来日した米国・変容貌修女会のシスター方が居住して幼稚園への奉仕活動の拠点となった、意義深い歴史を持つものでした。
時を経てナザレ修女会の仙台支部となり、また東北教区へと譲渡されてきました。その後も主教や司祭が居住されたり、東日本大震災前まで、宗教学者の山形孝夫氏(宮城学院女子大学長等を歴任)が「命を考える会」、ホスピス・ケアの会の会場とされる等、用いられてきました。大震災による被害と建物・諸設備全体の老朽化からその使用を止めましたが、大震災後の2年間は全国から集まる支援活動スタッフ・ボランティアの住居、活動拠点となって、まさに大活躍したことは、「ナザレの家」の記念にふさわしかったように思います。
昨年の臨時教区会で建物の解体、土地の売却が決定しており、この5月からは具体的な作業も進められようとしています。しかし、たんなる解体、売却ではなく、歴史を振り返りながら、小松島にある教会、幼稚園の働き、また同じように黙想・研修的な施設であった青葉静修館の働きを覚えての、新しい形へと繋がっていこうとしていますし、またそうでなければならないと思います。シスター方がおられた頃のことを良く知る信徒はもちろん、近隣の方も多く、やはり「ナザレの家」が一つの幕を降ろすことは残念と思われることでしょう。
良い形の記念を残すことが出来ますようにと願っています。
(教区主教)
あけぼの 2016年6月号
欅並木から 第7回「個人としては良い人」
 8月11日から15日まで、仙台で第7回日韓青年セミナーが開催されました。日本側の参加者11名、韓国から12名、それにスタッフも加わっての会合でした。司祭おひとりと青年4人は東北教区と交流を持つテジョン教区からの参加者でした。私は最終日前夜のふりかえりの会合に参加、そして15日の閉会礼拝の説教を担当しました。(8月15日に日韓の青年を前に説教するというのは試練でした)部分参加ですが、全体に和やかな雰囲気を感じました。韓国と日本の現在の難しい国際情勢・外交関係を思うと不思議な気持ちもします。
8月11日から15日まで、仙台で第7回日韓青年セミナーが開催されました。日本側の参加者11名、韓国から12名、それにスタッフも加わっての会合でした。司祭おひとりと青年4人は東北教区と交流を持つテジョン教区からの参加者でした。私は最終日前夜のふりかえりの会合に参加、そして15日の閉会礼拝の説教を担当しました。(8月15日に日韓の青年を前に説教するというのは試練でした)部分参加ですが、全体に和やかな雰囲気を感じました。韓国と日本の現在の難しい国際情勢・外交関係を思うと不思議な気持ちもします。
私自身、初めての韓国訪問、交流プログラムへの参加は1985年、6年だったと思います。東京教区とソウル教区の青年交流として、翌年には聖公会神学院のプログラムで訪韓しています。神学生同士の熱い交流で世の明けるまで語り合い、マッコルリを一つの椀で酌み交わし、雑魚寝をしました。当時の韓国は民主化闘争といわれる状況もあり、活動する教会の青年の中で逮捕されている人もいるという、そんな緊張感もありました。日韓関係の厳しさ、歴史問題からくる葛藤を抱えつつも、韓国と日本の青年、神学生の交わりは大変温かいものでした。
そういう中で、ふと言われた言葉が今も耳に残っています。「日本人は一人ひとりはとても良い人なのだけれど、国となった時に違ってくる。」本当にそうだろうなという思いを持ちました。個人的には皆良い人で、良心的で、友情も分かち合える。しかし日本という国として何かか発信されたときには違ってくると。現在はどうなのだろうか、あまり変わっていないのではないかと気にしつつ、しかしともかく顔を合わせて交流をし続ける意義の大きさは確信しています。 今年は日韓聖公会宣教協働30周年記念の年です。
欅並木から 第18回「やっぱり人!?」
 4月下旬に開催された宣教部会は、ゲストに東京の社会福祉法人葛飾学園理事長の山口千晴氏をお招きして、お話を伺う時を持ちました。実は私は東京教区の執事時代約7年間、葛飾にある葛飾茨十字教会(葛飾学園と同じ敷地)で主日勤務をしていたので、大変懐かしく思う一時でした。
4月下旬に開催された宣教部会は、ゲストに東京の社会福祉法人葛飾学園理事長の山口千晴氏をお招きして、お話を伺う時を持ちました。実は私は東京教区の執事時代約7年間、葛飾にある葛飾茨十字教会(葛飾学園と同じ敷地)で主日勤務をしていたので、大変懐かしく思う一時でした。
しかし私が関係した四半世紀前には葛飾学園という一つの保育園であった働きが、今や加えて10カ所に近い学童保育クラブと、さらに軽費老人ホーム・ケアハウス サンピエールおよび他に2か所の高齢者への奉仕の働きを展開しておられ、そのお働きからのお話を伺ったわけです。「すごい」と思わされますし、いろいろと具体的なご苦労も(そのほんの一部でしょうが)伺うことができました。その中での一言、こうした働きに不可欠のこととして「地元出身で、事業として、ライフワークとして、他の道を諦めて」献身する人が必要と言われたこと、そして何をやっても大変有能であろう同氏ですが、「他の道を諦めて」やってきたと、自分の人生、大変残念だとニヤッと笑いながら言われたのが印象的でした。
東北教区の働きは教会と共に幼児教育に大変重きをおいています。それを突き詰めていく道もあるでしょう。同時に高齢者に対する働きが機関としてはないことも気になっています。何をするにも「お金がない」と。しかし決してお金について楽観視するわけではありませんが、同じかそれ以上に、「人」なのでしょう。「他の道を諦めて!地域にしっかりと足を下ろして専念する人」。何事においてもそうなのだろうと思います。聖公会の聖職者は、異動していくことにプラスとマイナスもあるでしょう。一つの地域を動かない「特任」聖職の召命もありますが。むしろ聖職者に限らない、信徒の召命にこそ、将来の大きな可能性があるのかも知れません。
(教区主教)
あけぼの 2016年7月号
欅並木から 第5回「ヘイトクライム、ヘイトスピーチ」
 5月27日から29日まで、第61回の日本聖公会定期総会が開催され、29の報告、35の議案が審議されました。多くの重要な報告や議案はありますが今は一つだけ。「ヘイトクライム(人種・民族憎悪犯罪)、ヘイトスピーチ(人種差別・排外表現)の根絶と真の多民族・多文化共生社会の創造を求める日本聖公会の立場」を明らかにしようとの議案が審議され可決しました。その中で実際に路上で行なわれている「ヘイトスピーチ」の映像が紹介されたのですが、本当に凄まじいものでした。韓国・朝鮮の人たちへのものが中心でしたが、「いやがらせ」等というレベルを超えて、本当に「殺すぞ」「出てこい」と激しい声で絶叫し、実際に身の危険を感じさせるものでした。その絶叫している中には中学2年生の女子だという映像もありました。対象とされる国の学校の生徒等は、恐怖で堪ったものではなく本当に申し訳なく思いますが、同時にそうした日本の若い人は何故そうした行為に駆り立てられるのだろうかと思わされます。おそらく実際に韓国、朝鮮の人たちと利害関係にあって対立した経験は少ないだろうと思います。何でもいいから、何か異質、あるいは少数者と感じるものに思いっきり憎しみをぶつけたいのでしょうか。理由が乏しいだけに余計恐ろしく感じます。「誰でもいいから殺したかった」という言葉も最近聞く言葉です。世界170か国が「人種差別撤廃条約」に批准している中、日本もそれは入っていますが、こうした「ヘイトクライム・ヘイトスピーチ」を規制し、犯罪と認める条項には批准していない、わずか5か国の一つだそうです。日本聖公会と韓国聖公会は、今年宣教協働30周年の記念の年を迎えています。歴史認識等を巡る厳しい国際関係も知りつつ、しかし信仰の交わり、宣教協力の経験、友情を積み重ねてきました。短絡的にならずに一歩ずつ歩むことを日本社会全体が重んじる必要を感じています。
5月27日から29日まで、第61回の日本聖公会定期総会が開催され、29の報告、35の議案が審議されました。多くの重要な報告や議案はありますが今は一つだけ。「ヘイトクライム(人種・民族憎悪犯罪)、ヘイトスピーチ(人種差別・排外表現)の根絶と真の多民族・多文化共生社会の創造を求める日本聖公会の立場」を明らかにしようとの議案が審議され可決しました。その中で実際に路上で行なわれている「ヘイトスピーチ」の映像が紹介されたのですが、本当に凄まじいものでした。韓国・朝鮮の人たちへのものが中心でしたが、「いやがらせ」等というレベルを超えて、本当に「殺すぞ」「出てこい」と激しい声で絶叫し、実際に身の危険を感じさせるものでした。その絶叫している中には中学2年生の女子だという映像もありました。対象とされる国の学校の生徒等は、恐怖で堪ったものではなく本当に申し訳なく思いますが、同時にそうした日本の若い人は何故そうした行為に駆り立てられるのだろうかと思わされます。おそらく実際に韓国、朝鮮の人たちと利害関係にあって対立した経験は少ないだろうと思います。何でもいいから、何か異質、あるいは少数者と感じるものに思いっきり憎しみをぶつけたいのでしょうか。理由が乏しいだけに余計恐ろしく感じます。「誰でもいいから殺したかった」という言葉も最近聞く言葉です。世界170か国が「人種差別撤廃条約」に批准している中、日本もそれは入っていますが、こうした「ヘイトクライム・ヘイトスピーチ」を規制し、犯罪と認める条項には批准していない、わずか5か国の一つだそうです。日本聖公会と韓国聖公会は、今年宣教協働30周年の記念の年を迎えています。歴史認識等を巡る厳しい国際関係も知りつつ、しかし信仰の交わり、宣教協力の経験、友情を積み重ねてきました。短絡的にならずに一歩ずつ歩むことを日本社会全体が重んじる必要を感じています。
欅並木から 第20回「ルイジアナ主教をお迎えします」
 2005年の4月13日から19日まで、わたしたち―教区主教と信徒・聖職計10名はアメリカ聖公会ルイジアナ教区から、ニューオリンズにある主教座聖堂クライスト・チャーチの200周年記念礼拝にお招きいただいて参加してまいりました。ジェンキンス主教はじめ皆様から大歓迎を受け、特別な思い出となる訪問でした。
2005年の4月13日から19日まで、わたしたち―教区主教と信徒・聖職計10名はアメリカ聖公会ルイジアナ教区から、ニューオリンズにある主教座聖堂クライスト・チャーチの200周年記念礼拝にお招きいただいて参加してまいりました。ジェンキンス主教はじめ皆様から大歓迎を受け、特別な思い出となる訪問でした。
しかしその年、2005年8月に全米史上でも最大規模と言われるハリケーン・カトリーナがニューオリンズを中心にルイジアナを直撃、大災害となったことは皆様のご記憶にあると思います。わたしたちがホームステイでお世話になった瀟洒な街並みの美しい関係者のお宅も、すべて全壊しました。ルイジアナ教区の教区機能は他の街に避難移転。そこからジェンキンス主教は、大変な労苦をしつつこの大災害と向き合われたのです。「わたしたちは信仰に堅く立って揺るがない」という当時のメイルのメッセージは忘れられません。
2008年のランベス会議で再会し、その翌年には必ずご夫妻で東北を訪問されると言われていました。ハリケーンの時には東北教区は日本全体に復興支援募金を行い、約500万円近い献金をしていました。その感謝のお気持ちもあったと思います。しかしその後、再びハリケーンがルイジアナを襲い(これはカトリーナのような大被害にはなりませんでしたが)ジェンキンス主教は退任されました。
1892年に初めて青森にこられた宣教師、ミス・ジョージア・サザンはルイジアナ教区所属と言われます。その後、もちろんドレーパー司祭を通しての交流がありました。
ジェキンス主教の後継者モーリス・トンプソンJr.主教様も東日本大震災に思いを寄せてくださり、東北訪問を希望しておられました。このたび、それが実現することを喜び、皆様と共に歓迎したいと思います。
(教区主教)
あけぼの2016年10月号
※東日本大震災の際にトンプソン主教から送られた、再生を祈る写真
欅並木から 第4回「『文字数厳守』のこと」
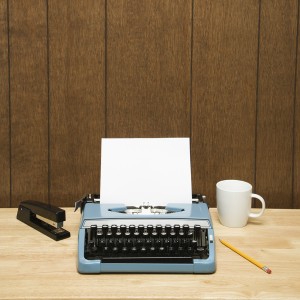 この『あけぼの』を毎月製作してくださっている広報委員会の労に感謝しています。またもちろん多くの方の協力、とくに寄稿がなければ出来ないことで、皆様に感謝いたします。充実した紙面ですが、少しデザイン的に写真が小さくないですかとか、文字が多過ぎませんか、と言うことがあります。その時の広報委員のお答の一つが、皆様からの原稿が、どうしてもお願いした字数より多くなるので、というものでした。いろいろと書くべき内容があるので当然とも思います。同時にわたし自身の自戒も含めて、印象的な話を思い起こします。
この『あけぼの』を毎月製作してくださっている広報委員会の労に感謝しています。またもちろん多くの方の協力、とくに寄稿がなければ出来ないことで、皆様に感謝いたします。充実した紙面ですが、少しデザイン的に写真が小さくないですかとか、文字が多過ぎませんか、と言うことがあります。その時の広報委員のお答の一つが、皆様からの原稿が、どうしてもお願いした字数より多くなるので、というものでした。いろいろと書くべき内容があるので当然とも思います。同時にわたし自身の自戒も含めて、印象的な話を思い起こします。
今では高名なある作家が若い時代、渾身の力を込めて書き上げた長編小説を大家に読んでもらったそうです。アドヴァイスは一言、「半分にしなさい」。その若い日の作家は怒りに震えましたが、しかし仕方なくその通りにして、やがてその作品は大きな賞を得て、出世作となりました。
「文章は短いほど良い」のが鉄則のようです。わたしは自慢ではありませんが、締め切りには遅れても文字数はぴったり依頼に合わせようと思ってきました。わたしも書くとまず長くなります(とくにパソコンで書くようになってから、その傾向があります)。しかし一度出来た後から、どうやって規定の文字数に合わせようかと奮闘します。同じことを重ねて言っていないか、もっと適切な表現はないか、平仮名を漢字にして詰められないか、何より内容が明瞭か。大体、自分が書きたいと思うことを書いている時には、つい勢いで言わなくても良いことまで書いていたりします。もう少し禁欲した方が、文章として良くなることの方がほとんどのようです。人に悪文を書かせるもっとも良い方法は、「制限なしで自由に書いてください」ということです。なにか自分の首を絞めるような話をしてしまいました。笑ってお許しください。
欅並木から 第21回「ルイジアナ教区主教をお迎えして」
 長く「祈りのパートナーシップ」として、親しい関係を保ってきましたアメリカ聖公会ルイジアナ教区のモーリス・トンプソン主教の東北ご訪問が無事に終わり、10月19日に帰国されました。
長く「祈りのパートナーシップ」として、親しい関係を保ってきましたアメリカ聖公会ルイジアナ教区のモーリス・トンプソン主教の東北ご訪問が無事に終わり、10月19日に帰国されました。
東日本大震災被災地としては新地・磯山、また野蒜(東松島市)方面へご案内、合わせて松島で日本的な雰囲気にも触れていただきました。八戸聖ルカ教会の宣教120周年記念礼拝、行事へのご参加、仙台の聖ルカ幼稚園への式典ご参加等、そして17日(月)には2時間にわたって、ルイジアナ教区のご様子を力を込めて語ってくださいました。
そうした中でルイジアナ教区が現在「回復」recovery ということを宣教のテーマとしておられることを伺いました。主教自身が、すでに40人の刑務所に服役中の人たちに堅信を授けられたこと、アルコール中毒や麻薬からの回復のプログラムにルイジアナ教区が力をいれておられる様子を伺いました。社会状況の違いもあるとは言え、やはり教会の働きの積極性に強い印象を受けました。ハリケーンのこと、東北の大震災のことも合わせて、広い意味で「回復」―失われたものを再び生かしていくこと―は教会の中心的テーマなのだと改めて感じさせられました。
そうした教会の働きの背骨は「信徒」であること、また「執事」には社会の必要を教会に伝える重要な役割があることも語られました。「信徒・執事・司祭・主教」は決して身分の違いなどではない。みんな同じ「洗礼の約束」に基づいた平等の関係であること、ただそれぞれに独自の役割を持っているのだとも。
毎週、代祷の中で覚えているルイジアナ教区が、ぐっと身近になってきた数日間でした。これからも祈りあう関係を続けること、そして機会があれば、お互いに訪ねあい、交わりを続けることを約束してお見送りいたしました。
(教区主教)
あけぼの2016年12月号
欅並木から 第3回「福音主義の教会は伸びている!?」
 3月15日に英国のサザク教区・主教座聖堂で行われた東日本大震災の記念礼拝に参加してきましたことは、今号「あけぼの」に特集されています。約1週間の短い訪問でしたが、その中で何度も耳にした言葉が「福音主義の教会は伸びている。伝統的な教会はそうではない」という主旨のものでした。「福音主義」という表現が正確かどうかわかりませんが、具体的には伝統的な祈祷書や祭服も用いず、音楽もギターやドラムのバンドが担い、自由なスタイルの説教や柔軟な形の信徒の参加の雰囲気が溢れている、そういう感じと言ってよいかと思います。今回訪ねた中にもそうした教会がありました。聖公会でも、他の教派でも、とくに聖公会の場合は伝統的な祈祷書の礼拝を続けている教会は、ご高齢の方々がほとんどという印象です。
3月15日に英国のサザク教区・主教座聖堂で行われた東日本大震災の記念礼拝に参加してきましたことは、今号「あけぼの」に特集されています。約1週間の短い訪問でしたが、その中で何度も耳にした言葉が「福音主義の教会は伸びている。伝統的な教会はそうではない」という主旨のものでした。「福音主義」という表現が正確かどうかわかりませんが、具体的には伝統的な祈祷書や祭服も用いず、音楽もギターやドラムのバンドが担い、自由なスタイルの説教や柔軟な形の信徒の参加の雰囲気が溢れている、そういう感じと言ってよいかと思います。今回訪ねた中にもそうした教会がありました。聖公会でも、他の教派でも、とくに聖公会の場合は伝統的な祈祷書の礼拝を続けている教会は、ご高齢の方々がほとんどという印象です。
どのように考えたらよいのか、わたし自身特別な意見を持ちあわせていません。絶対に伝統的なかたちは守るべきだと固く考えてもいないし、ギターやドラムにも抵抗はないけれども、それで礼拝をすれば「現代的」で若い人もどんどん教会に来るだろうとも、とくに日本においてはあまり思えないのです。少し理屈っぽい言い方をすれば、わたしたちには「神様の遠さ」と「近さ」、両方への思いがあるのではないかと思います。「静」としての神、「動」の神、「秩序」の神、「自由」の神。
月並みの言い方ですが、教会の礼拝にもいろいろあればよいのでしょう。主日の午前中には伝統的な形がしっかりと守られ、夕方にはギター等で若者(だけとは限りませんが)中心の礼拝、あるいは実験的な礼拝や新しい歌が多く歌われる礼拝・集会がある。そういうことは海外の教会、とくに主教座聖堂等では当たり前に行なわれていることと思います。様々に経験を広げていく寛容さが必要なのでしょう。

