教区報
主教コラム - 欅並木からの記事
欅並木から 第20回「ルイジアナ主教をお迎えします」
 2005年の4月13日から19日まで、わたしたち―教区主教と信徒・聖職計10名はアメリカ聖公会ルイジアナ教区から、ニューオリンズにある主教座聖堂クライスト・チャーチの200周年記念礼拝にお招きいただいて参加してまいりました。ジェンキンス主教はじめ皆様から大歓迎を受け、特別な思い出となる訪問でした。
2005年の4月13日から19日まで、わたしたち―教区主教と信徒・聖職計10名はアメリカ聖公会ルイジアナ教区から、ニューオリンズにある主教座聖堂クライスト・チャーチの200周年記念礼拝にお招きいただいて参加してまいりました。ジェンキンス主教はじめ皆様から大歓迎を受け、特別な思い出となる訪問でした。
しかしその年、2005年8月に全米史上でも最大規模と言われるハリケーン・カトリーナがニューオリンズを中心にルイジアナを直撃、大災害となったことは皆様のご記憶にあると思います。わたしたちがホームステイでお世話になった瀟洒な街並みの美しい関係者のお宅も、すべて全壊しました。ルイジアナ教区の教区機能は他の街に避難移転。そこからジェンキンス主教は、大変な労苦をしつつこの大災害と向き合われたのです。「わたしたちは信仰に堅く立って揺るがない」という当時のメイルのメッセージは忘れられません。
2008年のランベス会議で再会し、その翌年には必ずご夫妻で東北を訪問されると言われていました。ハリケーンの時には東北教区は日本全体に復興支援募金を行い、約500万円近い献金をしていました。その感謝のお気持ちもあったと思います。しかしその後、再びハリケーンがルイジアナを襲い(これはカトリーナのような大被害にはなりませんでしたが)ジェンキンス主教は退任されました。
1892年に初めて青森にこられた宣教師、ミス・ジョージア・サザンはルイジアナ教区所属と言われます。その後、もちろんドレーパー司祭を通しての交流がありました。
ジェキンス主教の後継者モーリス・トンプソンJr.主教様も東日本大震災に思いを寄せてくださり、東北訪問を希望しておられました。このたび、それが実現することを喜び、皆様と共に歓迎したいと思います。
(教区主教)
あけぼの2016年10月号
※東日本大震災の際にトンプソン主教から送られた、再生を祈る写真
欅並木から 第4回「『文字数厳守』のこと」
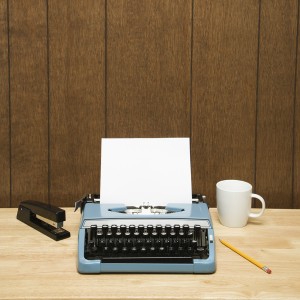 この『あけぼの』を毎月製作してくださっている広報委員会の労に感謝しています。またもちろん多くの方の協力、とくに寄稿がなければ出来ないことで、皆様に感謝いたします。充実した紙面ですが、少しデザイン的に写真が小さくないですかとか、文字が多過ぎませんか、と言うことがあります。その時の広報委員のお答の一つが、皆様からの原稿が、どうしてもお願いした字数より多くなるので、というものでした。いろいろと書くべき内容があるので当然とも思います。同時にわたし自身の自戒も含めて、印象的な話を思い起こします。
この『あけぼの』を毎月製作してくださっている広報委員会の労に感謝しています。またもちろん多くの方の協力、とくに寄稿がなければ出来ないことで、皆様に感謝いたします。充実した紙面ですが、少しデザイン的に写真が小さくないですかとか、文字が多過ぎませんか、と言うことがあります。その時の広報委員のお答の一つが、皆様からの原稿が、どうしてもお願いした字数より多くなるので、というものでした。いろいろと書くべき内容があるので当然とも思います。同時にわたし自身の自戒も含めて、印象的な話を思い起こします。
今では高名なある作家が若い時代、渾身の力を込めて書き上げた長編小説を大家に読んでもらったそうです。アドヴァイスは一言、「半分にしなさい」。その若い日の作家は怒りに震えましたが、しかし仕方なくその通りにして、やがてその作品は大きな賞を得て、出世作となりました。
「文章は短いほど良い」のが鉄則のようです。わたしは自慢ではありませんが、締め切りには遅れても文字数はぴったり依頼に合わせようと思ってきました。わたしも書くとまず長くなります(とくにパソコンで書くようになってから、その傾向があります)。しかし一度出来た後から、どうやって規定の文字数に合わせようかと奮闘します。同じことを重ねて言っていないか、もっと適切な表現はないか、平仮名を漢字にして詰められないか、何より内容が明瞭か。大体、自分が書きたいと思うことを書いている時には、つい勢いで言わなくても良いことまで書いていたりします。もう少し禁欲した方が、文章として良くなることの方がほとんどのようです。人に悪文を書かせるもっとも良い方法は、「制限なしで自由に書いてください」ということです。なにか自分の首を絞めるような話をしてしまいました。笑ってお許しください。
欅並木から 第21回「ルイジアナ教区主教をお迎えして」
 長く「祈りのパートナーシップ」として、親しい関係を保ってきましたアメリカ聖公会ルイジアナ教区のモーリス・トンプソン主教の東北ご訪問が無事に終わり、10月19日に帰国されました。
長く「祈りのパートナーシップ」として、親しい関係を保ってきましたアメリカ聖公会ルイジアナ教区のモーリス・トンプソン主教の東北ご訪問が無事に終わり、10月19日に帰国されました。
東日本大震災被災地としては新地・磯山、また野蒜(東松島市)方面へご案内、合わせて松島で日本的な雰囲気にも触れていただきました。八戸聖ルカ教会の宣教120周年記念礼拝、行事へのご参加、仙台の聖ルカ幼稚園への式典ご参加等、そして17日(月)には2時間にわたって、ルイジアナ教区のご様子を力を込めて語ってくださいました。
そうした中でルイジアナ教区が現在「回復」recovery ということを宣教のテーマとしておられることを伺いました。主教自身が、すでに40人の刑務所に服役中の人たちに堅信を授けられたこと、アルコール中毒や麻薬からの回復のプログラムにルイジアナ教区が力をいれておられる様子を伺いました。社会状況の違いもあるとは言え、やはり教会の働きの積極性に強い印象を受けました。ハリケーンのこと、東北の大震災のことも合わせて、広い意味で「回復」―失われたものを再び生かしていくこと―は教会の中心的テーマなのだと改めて感じさせられました。
そうした教会の働きの背骨は「信徒」であること、また「執事」には社会の必要を教会に伝える重要な役割があることも語られました。「信徒・執事・司祭・主教」は決して身分の違いなどではない。みんな同じ「洗礼の約束」に基づいた平等の関係であること、ただそれぞれに独自の役割を持っているのだとも。
毎週、代祷の中で覚えているルイジアナ教区が、ぐっと身近になってきた数日間でした。これからも祈りあう関係を続けること、そして機会があれば、お互いに訪ねあい、交わりを続けることを約束してお見送りいたしました。
(教区主教)
あけぼの2016年12月号
欅並木から 第3回「福音主義の教会は伸びている!?」
 3月15日に英国のサザク教区・主教座聖堂で行われた東日本大震災の記念礼拝に参加してきましたことは、今号「あけぼの」に特集されています。約1週間の短い訪問でしたが、その中で何度も耳にした言葉が「福音主義の教会は伸びている。伝統的な教会はそうではない」という主旨のものでした。「福音主義」という表現が正確かどうかわかりませんが、具体的には伝統的な祈祷書や祭服も用いず、音楽もギターやドラムのバンドが担い、自由なスタイルの説教や柔軟な形の信徒の参加の雰囲気が溢れている、そういう感じと言ってよいかと思います。今回訪ねた中にもそうした教会がありました。聖公会でも、他の教派でも、とくに聖公会の場合は伝統的な祈祷書の礼拝を続けている教会は、ご高齢の方々がほとんどという印象です。
3月15日に英国のサザク教区・主教座聖堂で行われた東日本大震災の記念礼拝に参加してきましたことは、今号「あけぼの」に特集されています。約1週間の短い訪問でしたが、その中で何度も耳にした言葉が「福音主義の教会は伸びている。伝統的な教会はそうではない」という主旨のものでした。「福音主義」という表現が正確かどうかわかりませんが、具体的には伝統的な祈祷書や祭服も用いず、音楽もギターやドラムのバンドが担い、自由なスタイルの説教や柔軟な形の信徒の参加の雰囲気が溢れている、そういう感じと言ってよいかと思います。今回訪ねた中にもそうした教会がありました。聖公会でも、他の教派でも、とくに聖公会の場合は伝統的な祈祷書の礼拝を続けている教会は、ご高齢の方々がほとんどという印象です。
どのように考えたらよいのか、わたし自身特別な意見を持ちあわせていません。絶対に伝統的なかたちは守るべきだと固く考えてもいないし、ギターやドラムにも抵抗はないけれども、それで礼拝をすれば「現代的」で若い人もどんどん教会に来るだろうとも、とくに日本においてはあまり思えないのです。少し理屈っぽい言い方をすれば、わたしたちには「神様の遠さ」と「近さ」、両方への思いがあるのではないかと思います。「静」としての神、「動」の神、「秩序」の神、「自由」の神。
月並みの言い方ですが、教会の礼拝にもいろいろあればよいのでしょう。主日の午前中には伝統的な形がしっかりと守られ、夕方にはギター等で若者(だけとは限りませんが)中心の礼拝、あるいは実験的な礼拝や新しい歌が多く歌われる礼拝・集会がある。そういうことは海外の教会、とくに主教座聖堂等では当たり前に行なわれていることと思います。様々に経験を広げていく寛容さが必要なのでしょう。
欅並木から 第22回「信徒の分餐奉仕」
 東北教区の信徒奉事者の働きの中に「分餐奉仕協力」を加えることとなり、すでに数名の方が教会委員会、常置委員会を経て、主教の認可を得ておられます。各国の聖公会では幅広く、また日本聖公会でもすでに行われていますが、東北教区では初めての経験となります。
東北教区の信徒奉事者の働きの中に「分餐奉仕協力」を加えることとなり、すでに数名の方が教会委員会、常置委員会を経て、主教の認可を得ておられます。各国の聖公会では幅広く、また日本聖公会でもすでに行われていますが、東北教区では初めての経験となります。
聖餐式はもちろん教会にとって最も重要な礼拝です。一方、重要視するあまり、その中で聖別される「聖体」(聖別されたパンとブドウ酒=御体と御血)に対する信仰が過剰に強調され、中世期にはやや迷信的ともなって、そのことがカトリックとプロテスタントの分裂の原因となった歴史もあります。聖職者でなければチャリス(杯)やパテン(皿)に触れることも出来ないと教えられた時代もありました。「聖体」がキリストの真の体であるということ、それはわたしたちの信仰です。しかし同時に聖書でパウロが一生懸命語っている「キリストの体」は教会のこと、わたしたちのことです。またキリストの臨在は「聖体」だけではなく「み言葉」、聖書の中にも認められるべきものです。聖書朗読が重要な理由もそこにあります。
「キリストの体」である教会の中で、祭司的な務めを分かち合う信徒も共に、「聖体」を分かち合う奉仕に参加すること。その意義は大きいと思います。陪餐者数が多いから、あるいは司祭がご高齢で補佐が必要だから、という現実的理由もあっていいでしょう。しかしそれだけではなく、今申し上げたことも心に留めてくださって、この奉仕がますます豊かになっていくようにと願います。さらには信徒の方が聖体を持って病床の方をお訪ねし、一緒にお祈りするようなことも出来れば。
東北教区の未来は、教会全体がそれぞれの賜物を生かし合いながら、豊かに奉仕職を分かち合う、そのことにかかっていると信じています。
(教区主教)
あけぼの2017年5月号
欅並木から 第2回「川端先生と今橋先生 〜日本キリスト教団に属するお二人の先生のこと〜」
 川端純四郎先生は、昨年2013年5月に逝去されました。東北学院キリスト教科の教員として、ドイツに留学された神学者ですが、同時にバッハの研究家として名著を著し、教会のオルガンも弾き、賛美歌を愛されたご生涯でした。さらに原発への反対、憲法9条を守る運動についても指導的な方でした。内には大変強い情熱を秘められながら、しかし本当に温厚な方で、わたしは『礼拝と音楽』という雑誌の編集企画委員として10年ほどお付き合いをさせていただきました。一度仙台駅でお見かけした時、「アレッ、大江健三郎かな」と思ったと言えば、なんとなく風貌が浮かばれるかもしれません。『3・11後を生きるキリスト教』(新教出版社)という著書も出されました。
川端純四郎先生は、昨年2013年5月に逝去されました。東北学院キリスト教科の教員として、ドイツに留学された神学者ですが、同時にバッハの研究家として名著を著し、教会のオルガンも弾き、賛美歌を愛されたご生涯でした。さらに原発への反対、憲法9条を守る運動についても指導的な方でした。内には大変強い情熱を秘められながら、しかし本当に温厚な方で、わたしは『礼拝と音楽』という雑誌の編集企画委員として10年ほどお付き合いをさせていただきました。一度仙台駅でお見かけした時、「アレッ、大江健三郎かな」と思ったと言えば、なんとなく風貌が浮かばれるかもしれません。『3・11後を生きるキリスト教』(新教出版社)という著書も出されました。
今橋先生は今年1月に帰天された、日本キリスト教団の牧師、神学者です。川端先生同様、日本キリスト教団の礼拝と讃美歌に関する優れた指導者であられました。東京の目白にある聖書神学校の校長も務められましたが、聖公会の礼拝の伝統に対しても温かい関心を持ち続けられ、私も何度か学びの時をご一緒することがありました。最後の出版となった書物は、聖公会のオックスフォード運動の指導者の一人、詩人であったジョン・キーブルの詩集の翻訳でした。『光射す途へとー教会歴による信仰詩集』(日本キリスト教団出版局)です。最後の書評を書く光栄を与えられましたが、是非皆様にもご紹介したく思います。なじみ深い朝の聖歌「来る朝ごとに」、夕の聖歌「わがたまの光」、そして「心清き人はつねに」等、キーブルの詩数曲が『日本聖公会聖歌集』に入っています。
優れた他教派の先生方との交わりとその恵みを覚えたく、ここに書かせていただきました。
欅並木から 第23回「オ~、お互いを忍耐して~」
かつてわたしはカトリックの学校で学ぶ機会を与えられました。いわゆる「典礼学」(聖公会では礼拝学)の当時の大家・土屋吉正神父のもとで学ぶためでした。もう四半世紀も前ですが、当時そこにはなかなか優れた内外の神学者が揃っておられたと思います。そのお一人がペトロ・ネメシェギ神父という方で、世界のローマ・カトリック教会の神学会議にも属する、イエズス会の司祭であられました。その方の講義が充実していたのは勿論ですが、時に教会や修道会のことをユーモラスに語られることもありました。ある時の話。
「修道院は大変で~す。世界中の修道者が集まっています。ドイツ人は理屈ばかり言っていま~す。イタリア人とアメリカ人はいつもうるさい、賑やかで~す。英国人は頑固で~す。日本人はむっつりと黙っていま~す。でもわたしたちは~お互いを忍耐して~、神様の栄光を顕すので~す!!」。
教室は笑いに包まれました。もっとも信仰的な成熟した共同体である筈の修道会、修道院です。しかし、ただ皆が気心が知れて仲良しなのではない、まったくありませんと。しかも修道院は基本的には一生付き合うのですから大変そうです。しかし「お互いを忍耐して、神様の栄光を顕す」のですと。
わたしは笑いながら、大変印象的な言葉として記憶しました。お互いに仲良く、すべてを認めあえていれば理想的でしょう。しかし修道院でもそんなことはない。いやイエスの十二使徒でさえ、まったくそうではないようです。
多様であるということは時にお互いに忍耐を要する、ということと同義なのではないかとさえ思います。それでも同じ神様に召され、「神の栄光を顕すために」、その大きな目的の中に召されているのです。
わたしたちの中ではどうでしょうか?
(教区主教)
あけぼの2017年6月号
* 主教コラム「欅並木から」は今号をもって終了いたします。ご愛読、ありがとうございました。
欅並木から 第1回「主教コラム(初回はタイトル未定でした。)」
 かつては「旅する教会」と「台原だより」をこの「あけぼの」に連載していました。「旅する教会」はその後単行本になり、いくつかの教会の読書会等でも用いてくださったとか、感謝しています。主教としての日々の雑感や折々の事柄を綴っていた「台原だより」は東日本大震災の発生の中で途絶えていました。
かつては「旅する教会」と「台原だより」をこの「あけぼの」に連載していました。「旅する教会」はその後単行本になり、いくつかの教会の読書会等でも用いてくださったとか、感謝しています。主教としての日々の雑感や折々の事柄を綴っていた「台原だより」は東日本大震災の発生の中で途絶えていました。
大震災から三年目を迎える今、決して余力が出来てきたわけではありませんが、やはり少しずつ書かせていただこうということになりました。タイトルは未定です。
さて、東北教区主教座聖堂・仙台基督教会の新しい礼拝堂、教区と教会の施設がいよいよ完成、3月1日に聖別式ということになりました。仙台における伝道の開始は一八九四年、民家から出発し、一九〇五年に現在地に「新築会堂聖別式挙行」、一九三四年に東北地方部の大聖堂に、そして一九四五年七月、仙台大空襲により焼失という歴史を持っています。今回も古い赤レンガが発掘され、記念されようとしています。前の聖堂は一九五七年に聖別されていますが、一九七八年の宮城沖地震等によって被害を受けてもいます。いずれの教会でもそうですが、歴史を感じます。建物の歴史もそうですが、その中で祈り続けてきた信徒の信仰と祈りの歴史があります。
教会の建築というのは大変です。個人の家や会社とは違った意味で、一人一人の信仰に基づいた思いがあります。それをまとめてきた関係者の労苦に敬意を表し感謝します。建物が完成した後も、様々な課題は出てくるでしょう。しかし皆が祈り続けながら、癒しと和解と回復の家としての中身を作り上げていかなければならないのだと思います。大震災の中で、全国の多くの人に祈られ支えられてきた聖堂としての新しい歴史が始まるのでしょう。
欅並木から 第8回「分けあったミカン」
 10月に韓国・済州島で開催された日韓聖公会宣教協働30周年記念大会で、テジョン教区の主教被選者ユ・ナッジュン師とお会いすることができました。ほぼ初対面の同師ですが、まったく些細な、しかし印象的な出来事を一つ。
10月に韓国・済州島で開催された日韓聖公会宣教協働30周年記念大会で、テジョン教区の主教被選者ユ・ナッジュン師とお会いすることができました。ほぼ初対面の同師ですが、まったく些細な、しかし印象的な出来事を一つ。
たまたま小さなミカンを一つ手にとっておられた同師(済州島はミカンが銘産)、わたしの方に歩み寄って来られながら剥いたミカンを割って、数房をヒョイとわたしに差し出されました。それだけのことですが、皆さんはいかがですか?わたしはあまり一つのミカンを分け合って食べた経験はないように思います。そしてそれはユ師だけではなく、大会中、ミカンを食べている人の傍にいると、必ずヒョイと数房分けてくれるのです。
大会中、別の機会に大韓聖公会ソウル教区主教、首座主教の金根祥師父と何人かで食事をしていた時、魚の食べ方の話から韓国と日本の食事のマナーの話になりました。韓国では一匹の魚に、何人もが箸を出して一緒に食べるのは普通です。日本人は一人できれいに骨だけ残して食べてしまいます。そうでないと行儀が悪いことにもなるでしょう。韓国ではかなり身を残したまま、魚が下げられることがありますが、「残した部分は、貧しい人の取り分なんだ」と金主教。現在はそういう貧しい人はいないかも知れませんが、しかしそれは『レビ記』にも見られる思想です(19章)。一人一人が自分の皿に自分の分の食べ物を載せ、それは自分できれいに食べ尽くす、というのは、「だから日本人は親しくなりにくい」と、今は大変親しい金主教の言葉でした。
「分かち合う」感覚について、韓国と日本の違いのようなものを感じた瞬間でした。小さなパンを割って食べ、杯を回し飲みするのが聖餐式だとすれば、大変近いものを感じます。
教区主教
あけぼの 2014年12月号
欅並木から 第9回「大切なことに向けて -予告的な話-」
 11月号のこのコラムで、日本聖公会が祈祷書改正に向けた準備を始めているとお伝えしました。同時に日本聖公会総会では審議、報告されていることで、教会の信仰生活に関わる大切なことが今動き出そうとしています。今回は短い紙面ですので、ごく予告的に事柄を紹介して、新年の号で改めて詳しいお話をしたいと思います。
11月号のこのコラムで、日本聖公会が祈祷書改正に向けた準備を始めているとお伝えしました。同時に日本聖公会総会では審議、報告されていることで、教会の信仰生活に関わる大切なことが今動き出そうとしています。今回は短い紙面ですので、ごく予告的に事柄を紹介して、新年の号で改めて詳しいお話をしたいと思います。
聖公会は長い伝統の中で、洗礼だけではなく主教の按手による「堅信を受けた者、またその準備を終えて主教から特別の許可を受けた者は、陪餐することができる」(祈祷書285頁)としてきました。中世のキリスト教世界において幼児洗礼が主流となり、幼児洗礼を受けた子どもが、一定程度大きくなったら教会問答を学んで堅信を受け、そして聖餐に与る、という流れが固定していました。しかし洗礼の意味をもう一度考えてみると、それは教会の家族の一員、キリストの体となることです。家族の一員となったけれども一緒に食卓につけない、一緒に食事をしないということはやはり再考しなければならないことです。20世紀になって多くの研究や議論を経ながら、現在各国聖公会やローマ・カトリック教会でも、洗礼を受けた人(幼児も)は陪餐できるようにという変化が起こっています。洗礼の意味の重大さが見直され、子どもも含めて主の食卓に早い機会から多くの人が招かれるようにと願われています。そして堅信は一言で言えば、主教の按手によって強められ祝福され、教会の宣教の業に参与していく派遣の意味を持つことになるでしょう。
まだ時間をかける必要もある大切な課題です。現在、管区の礼拝委員会で「Q&A」作成等の作業等が進められています。今まで大切にしてきた伝統や考え方があります。冷静に、そして前向きに、ご一緒に考えていきたいと願います。
教区主教
あけぼの 2015年1月号

