教区報
主教コラム
「昨日も今日も、また」2026年2月
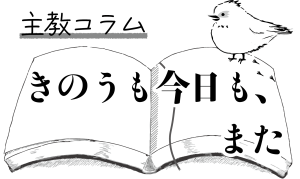
昨年10月22日、北関東教区小山祈りの家に併設の北関東教区墓地に関係者が集い、聖ヨハネ修士会(SSJE)日本管区解散50周年記念および逝去者記念式が献げ
られました。小山修道院創立(1935年)と創生に尽力されたケネス・アボット・ヴァイアル主教も記念されました。
師は1893年12月19日米国マサチューセッツ州に誕生。ハーバード大学、ジェネラル神学院、ハーバード大学院に学び、1919年少年期より強い志望であった修道生活を求め聖ヨハネ修士会に入り、1923年ボストン郊外ケンブリッジの修士会本院にて終生誓願。1935年来日、聖三一教会米人会衆管理、立教大学と聖公会神学院講師、等。1940年帰米。1947年米国聖公会駐日代表として再来日、日本聖公会復興事業従事、聖公会神学院校長。1951年東京教区補佐主教、1955年引退。米軍チャプレン。東京東久留米修道院開設、修院長。小山修道院長、修士会日本管区長。1974年1月3日大聖病院で首座主教大久保直彦主教、後藤真主教らが見守る中、永眠。80歳。1月9日東京教区葬。3月7日東久留米修道院礼拝堂にて逝去者記念式埋骨式。白木の墓標は竹田鐵三神父の筆に依るもので、「遺骨はこの墓標の下に納められる。彼の願いが叶い日本の土、修道院の庭に眠る。アアよかった。ソノために彼は内心苦労したようであった。」と追悼。
十和田湖畔ヴァイアル山荘は1934年に修士会が「招仙閣」を譲り受け黙想の場とし、1976年東北教区に寄付。この地を愛された主教の名を後世に残すため「ヴァイアル山荘」と改名し、現在に至る。
戦後の日本聖公会の霊的再生に尽力された主教、「静かな中にも篤き信仰、福音の行動者であった」主教の存在を、私たちは山荘がある限り語り継いでいきたいと思います。師のパラダイスにおける平安をお祈りします。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2025年11月
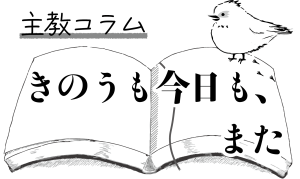
長い長い猛暑、酷暑の今夏でした。暑すぎるという理由で、例年は8月に開いている仙台聖フランシス教会日曜学校恒例の「夏の学校」は、9月27日(土)に時期をずらして「秋の学校」と名称も変更しての開催となりました。
参加者は年長児から中学1年生まで35人、聖クリストファ幼稚園の在園児と卒園生です。
スタッフは先生や老若信徒の12人で、準備や運営、ご奉仕に感謝でした。
プログラムは礼拝、自己紹介、聖書の話、カレーライス作り、ゲーム、十字架のキーホルダー作りと盛りだくさんな内容でした。子どもたちは疲れを知らず、思いっきり楽しんでいました。誰もが生まれた時から知っている友だち、仲間、兄弟姉妹のように和んでいて驚きでした。
今回のテーマソングは「主イエスとともに 歩きましょう どこまでも いつも」で礼拝と聖書の時間に、私は2枚の絵画をお見せしました。何せ幼稚園児さんから中学1年生までと幅広いので、視覚に訴えたのです。
1枚は、主イエスとメナスさんが並んで描かれている「友情のイコン」です。どちらがイエス様でしょう?とクイズにし、正解は背後の円光で内側に十字が描かれているほうですと解説しますと、なるほどと納得の様子。イエス様の右手がメナスさんの肩に回されていると説明しますと、二人はお友だちなんだとみんなにっこりでした。
2枚目は、ロバート ツンドの『エマオへの道』(1877年頃作品)です。この絵画が、聖クリストファ幼稚園の廊下の一角に飾られていたのを知らなかった私はビックリして利用したのです。しかもこの額縁は青葉静修館にあったもので、深い神様のお導きに感動しながらルカ24章13〜35節で、ご復活のイエス様が二人のお弟子さんと同行しているように、私たちとともに歩んでおられるのを想像して、子ども賛美歌「エマオの道を 旅ゆくふたり」を皆で歌いました。
(教区主教)
「昨日も今日も、また」2025年10月
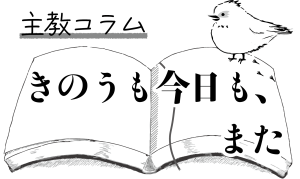
8月8日夜、入所先の介護施設の一室で、可愛い娘3人に看取られながら、妻の母が老衰で息を引き取りました。90歳でした。
37年前、和歌山県新宮市の自宅で、おそらく早くに亡くした夫を偲びながら、長女との結婚をお許しいただいた義母でした。牧師とその妻とは皆目見当がつかなかったはずです。まさか東北にまで行くなんて想定外だったでしょう。1991年3月、母は1歳と2歳の孫二人の引っ越しで、まだ寒さの厳しい会津若松まで来てくれ有難いことでした。
2021年になって、母と次女との自宅暮らしが覚束ないと身内から連絡が入り、青森聖アンデレ教会委員会に相談の上、5月に「青森に行こう!」と飛行機に乗せて牧師館に居を移しました。エアコンを設置、暖房を整えていただいた教会の皆様には本当に感謝しかありません。母は軽いアルツハイマー型認知症との検査結果でしたが、信徒のお医者さんにかかれて安心し、デイサービスを利用して日々にこやかに暮らしていました。
2024年4月、仙台聖フランシス教会牧師館に引っ越し、青森時代のようにデイサービスを受けていましたが、次第に衰えはじめ、食事もだんだん取れなくなり、今年1月誤嚥性肺炎で3日間入院、2月脱水症状を発症し50日間の24時間付き添い入院、退院後は在宅医療で過ごし、最後の39日間はショートステイをして介護施設におりました。
在宅療養中、兵庫県で働いている三女が4月から3カ月介護休暇を取って一緒に生活し、仕事復帰後も往来を繰り返していましたが、再来した日の夜に三姉妹たちが揃っている中での最期になりました。穏やかで静かなお別れでした。
主教になった私の紫シャツ姿に、母はいつも必ずニヤニヤしては、「赤いよ~」と言って嬉しがっていたのがいつまでも残っています。それは今、母からの激励・応援の声のように響いています。
(教区主教)
