教区報
教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事
「教会 ー 一歩踏み出す拠点」 あけぼの2019年4月号
 若松諸聖徒教会は、震災後、園舎建替に伴って旧聖堂を取り壊して以降、聖堂をもたず幼稚園ホールにて礼拝を守っています。ホール舞台上には祭壇も常設されており、小さいながらベストリーに利用できる部屋もあります。礼拝を行う度に会衆席用の椅子を並べたり片付けたりする労はあるものの、取り立てて「不便」を感じてはいません。それでも今、私たちの教会は教会建設を祈り求めています。
若松諸聖徒教会は、震災後、園舎建替に伴って旧聖堂を取り壊して以降、聖堂をもたず幼稚園ホールにて礼拝を守っています。ホール舞台上には祭壇も常設されており、小さいながらベストリーに利用できる部屋もあります。礼拝を行う度に会衆席用の椅子を並べたり片付けたりする労はあるものの、取り立てて「不便」を感じてはいません。それでも今、私たちの教会は教会建設を祈り求めています。
毎主日の礼拝では10人程の出席者数の小さな群れに、教会建設などという大事業に着手する「体力」はあるのか?仮に新聖堂が与えられたとして、潤沢な資金があるわけではない現状、後代に借金を残すだけになるのではないか?正直に告白すると、そうした負の心情だけが管理牧師時代からの偽らざる思いでした。
そんなとき思い出したのは村上達夫主教の「私たちはこの礼拝堂がなぜ今ここに建っているのかという本来の目的をもう一度深く考えてみることが大切」との言葉が記されていた『若松諸聖徒教会小史』です。1986年、今は取り壊された聖堂建設60年を迎えた年に刊行された本書をあらためて読み返すと、興味深い記事が目に留まりました。
教会創立10年を経た頃、若松諸聖徒教会は南会津への「特別伝道行脚」を始めています。先書にはそのいきさつについてこう記されています。「南会津巡回という特別伝道行脚について一言すべきであろう。そもそも南会津郡および大沼郡の二郡は本県中最も不便な山奥で、人口も疎らで、しかも広範に亘っている。このような地方を巡回しなければならなくなったのは、次のような理由による。明治の中葉、只見川沿岸一帯に甚だしい凶作飢饉があり、その惨状は深刻を極めた。岡山孤児院の石井十次氏はこの東北の悲報に接し、孤児救済のために郡山へ来た」(同書5頁)。しかしこの子どもたち30名は、石井十次氏の施設が定員に達したこともあり、結果としては岡山にではなく大阪の博愛社で引き受けられることになります。数十年後、成人したこの子どもたちは故郷に戻りますが、博愛社での生活で受洗、信仰者となっての帰郷でした。当時、若松諸聖徒教会の長老であったメードレー長老はこのいきさつを知り、30名の信仰者がいる場所への牧会を思い立たれたのだと言います。そして「一巡七十里、その経費と20日の日数もさることながら、天下有数の嶮所難所を越え、旅館の設備もないところを、時には令夫人をも伴って巡回され、牧者としての任務を遂行された」(同書6頁)そうです。南会津巡回を継承したマキム長老に至っては「駒止峠から沢に落ちて命拾いしたこと、旅館(マキム長老時代にできた模様)にマキム長老に合う衣類や夜具がなく大騒ぎしたこと等々」も記されており、同師が南会津の「多くの人々に慕われた師」(同書7頁)であったことも記されています。
私たちの教会の信仰の先達が南会津へと一歩踏み出したように、祈りによって励まし合いつつ、キリストの派遣に応えて地域社会に一歩踏み出す「拠点」としての教会が与えられるなら…それが「今」の私たちの願いです。私たちの会津若松での歩みを覚えて、みなさまにもご加祷いただければ幸いです。
若松諸聖徒教会牧師
司祭 ヨハネ 八木 正言
あけぼの2021年1月号
巻頭言「サイレントナイト」
「今年のクリスマスはやめにしませんか」そんな提案を教会役員会にぶつけたのは、私が聖ペテロ伝道所に勤務していた時、近くのプロテスタント教会に勤務していた若い牧師さんでした。当然の如くに「何をいっているのだ」と役員さんたちは反発します。この牧師さん、少し言葉が足りなかったようで、いいたかったのは降誕日の礼拝をしないということではなく「例年のように派手な飾りつけや、ご馳走を囲んだパーティーをやめましょう」ということだったようです。
イエス様は、身重のマリアさんとヨセフさんが住民登録をするためにナザレからベツレヘムに向かう途中で、宿も取れない中で、貧しい家畜小屋でお生まれになりました。まさに「人みな眠りて、知らぬまにぞ」(聖歌第85番2節)と歌われている通りの状況でした。
最近知って驚いたのですが、イスラエルにも雪の積もる山があり、スキー場もあるのだとか。イエス様のご降誕が本当に12月なのかは定かではありませんが、平地でも夜は冷えた ことでしょう。暗くて寒くて静まり返った闇の中、落ち着いて赤子を寝かせることもかなわず、両親とてもゆっくりと横たわることができなかったことでしょう。想像するだけで寂しさがこみ上げてきます。
 多くの人たちが「クリスマス」と聞いて思い浮かべる光景とは、まったく違ったみ子のご降誕の姿がそこにはありました。わたしたちは降誕日前夕の礼拝(イヴ)の中で、その時の場面を垣間見ているのかもしれません。必要最低限の光しか用いられないのは、雰囲気作りなどではなく、きっと2千年前の「その場」にわたしたちも繋がれるためではないでしょうか。神の示された「時」に確かに私たちもみ子と共に存在しているのです。クリスマスには毎年繰り返す「祭り」としての意味もあるでしょう。何度となく繰り返してきたクリスマスですが、同時に毎年私たちはみ子イエスの誕生の瞬間に招かれているということも、信仰の真実ではないかと思うのです。
多くの人たちが「クリスマス」と聞いて思い浮かべる光景とは、まったく違ったみ子のご降誕の姿がそこにはありました。わたしたちは降誕日前夕の礼拝(イヴ)の中で、その時の場面を垣間見ているのかもしれません。必要最低限の光しか用いられないのは、雰囲気作りなどではなく、きっと2千年前の「その場」にわたしたちも繋がれるためではないでしょうか。神の示された「時」に確かに私たちもみ子と共に存在しているのです。クリスマスには毎年繰り返す「祭り」としての意味もあるでしょう。何度となく繰り返してきたクリスマスですが、同時に毎年私たちはみ子イエスの誕生の瞬間に招かれているということも、信仰の真実ではないかと思うのです。
そう考えると、礼拝が終わり「さー、次行ってみよう!」とパーティーに切り替えるのは、なんだか惜しい気がしてしまいます。もちろんそこには宣教的な意味もあるわけですから、単純には否定できないことですが、たまにはみ子のご降誕の場に居合わせた余韻を静かに感じる時があっても良いのではと思います。冒頭で紹介した牧師さんにも、そんな思いがあったのかもしれません。
そういう意味で今年のクリスマスは千載一遇の時です。
祝会をどうするかと意見を交わすまでもなく、結果は見えてしまっています。残念といえばその通りなのですが、礼拝が終わって「残念だね」とか「さみしいね」といって感染症を呪って帰るのではなく、まさに今年の降誕節は「静かな夜・サイレントナイト」に思いを寄せてみなさいという、神様からの恵みの時なのだと捉えられないでしょうか。どんな時でも、み子のご降誕は救いの時、恵みの時であることに変わりはないのです。
そして今年は聖家族がヘロデからの迫害を逃れたエジプト逃避行、み子のための幼き殉教者、東方からの訪問者などにも思いを馳せ、降誕の出来事を黙想する中で、豊かな恵みが与えられそうです。
司祭 ステパノ 涌井 康福(秋田聖救主教会 牧師)
あけぼの2022年12月号
巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「神は人を自分のかたちに創造された。(創世記より)」
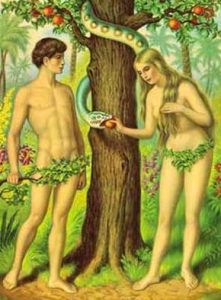 10月に人生初の入院をしました。左掌に瘤状のものができ、関節や腱を滑らかに動かすための滑油が溜まる「ガングリオン」という腫瘤だろうと思いしばらく放置していましたら、人差し指と中指にしびれや痛みがおこりだしました。右手は使えるのですが仕事や生活に支障をきたすようになり受診したところ、「血管腫」という腫瘍であることがわかりました。良性腫瘍でしたが、痛みなどは神経が圧迫されているからということで、手術を受けることになりました。手術は約2時間ほどでしたが総延長(?)約10センチほどメスが入ったので、家に帰ってから大量の出血があってはまずいからと1泊入院となりました。いつ退院できるのかわからないということではないので、入院とはいってもそれほど緊張することはなかったのですが、これまで入院されている方をお見舞いした時とは反対の視点で、病室の天井を見つめることになりました。しかも腕には点滴の管が刺さっていますので不自由な状態です。入院されていた方たちはこういう視点で訪れた私たちを見ておられたのだなと、少しだけですがその気持ちがわかった気がしました。
10月に人生初の入院をしました。左掌に瘤状のものができ、関節や腱を滑らかに動かすための滑油が溜まる「ガングリオン」という腫瘤だろうと思いしばらく放置していましたら、人差し指と中指にしびれや痛みがおこりだしました。右手は使えるのですが仕事や生活に支障をきたすようになり受診したところ、「血管腫」という腫瘍であることがわかりました。良性腫瘍でしたが、痛みなどは神経が圧迫されているからということで、手術を受けることになりました。手術は約2時間ほどでしたが総延長(?)約10センチほどメスが入ったので、家に帰ってから大量の出血があってはまずいからと1泊入院となりました。いつ退院できるのかわからないということではないので、入院とはいってもそれほど緊張することはなかったのですが、これまで入院されている方をお見舞いした時とは反対の視点で、病室の天井を見つめることになりました。しかも腕には点滴の管が刺さっていますので不自由な状態です。入院されていた方たちはこういう視点で訪れた私たちを見ておられたのだなと、少しだけですがその気持ちがわかった気がしました。
わたしは元来暢気すぎる傾向があり、不調を覚えてもすぐに受診することはありませんでした。しかし気が付けばもう高齢者の域に達しており、今回も術後に運転ができずに多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。改めて自分のためばかりではなく、体は大事にしなければいけないと思わされた経験でした。
話は過去に飛びますが、牧師になる前に働いていたところは教会関係の保育園で、保育士の約8割が信徒という職場でした。様々な教派の方が在職していましたが、その中には福音派の方もいて、職員旅行などでアルコールが出てきても口にすることはありませんでした。聖公会では牧師もお酒を飲んだり、タバコを吸う人がいることに驚いていましたが、ことあるごとに「神様から与えられた体を傷つけたり、汚したりしてはいけないと教えられている」と話していました。聖公会の面々は「ずいぶん厳しいね」とか「イエス様だってのんでたんだよね?」とかささやいていましたが、食物規程のようなものは別として「神様から与えられた体・命」ということは教派ごとの考えに関係なく、心に留めておかなければいけないことだと思います。もしかしたら健康に少し無頓着な私からは、いつの間にか「神から与えられた」という大事なことが抜け落ちていたのかもしれません。私ばかりではない。周りの人たちもすべて神から命を与えられた存在として見つめることができたなら、世の中はもう少し平和になるのかもしれませんね。命も体も私のものであるようで私のものではない。そのことを忘れたり、知ろうとしないのはとても恐ろしいことなのではないでしょうか。
「なぜ人を殺してはいけないのか」という少年からの疑問に対して、答えに窮した大人がいたという話を聞いたことがあります。「法律で決まっているから」だけでは愛がありません。「神様がお与えくださった命だから」という答えも、すぐには受け入れられないでしょう。それでもあきらめることなく、主の平和のために伝え続けることが信仰であり、宣教なのだと思います。
秋田聖救主教会牧師 司祭 ステパノ 涌井 康福
あけぼの2025年4月号
巻頭言 イースターメッセージ「復活の朝」
イースターおめでとうございます。ご復活の主の祝福が皆様にありますように!
 金曜日に十字架に掛けられて息を引き取られたイエス様は、アリマタヤ出身のヨセフとニコデモがユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて亜麻布で包んで、その日のうちに慌ただしく墓に葬られました。何故ならユダヤ人の安息日、つまり土曜の前日であり、11人の弟子たちはユダヤ人を恐れ隠れてしまったからです。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、一緒にいた他の女たちは、ご遺体に丁寧に接し、手厚く葬りの用意をしたかったけれども叶いませんでした。
金曜日に十字架に掛けられて息を引き取られたイエス様は、アリマタヤ出身のヨセフとニコデモがユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて亜麻布で包んで、その日のうちに慌ただしく墓に葬られました。何故ならユダヤ人の安息日、つまり土曜の前日であり、11人の弟子たちはユダヤ人を恐れ隠れてしまったからです。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、一緒にいた他の女たちは、ご遺体に丁寧に接し、手厚く葬りの用意をしたかったけれども叶いませんでした。
2日を過ごし、週の初めの明け方早くになりました。安息日が明けるのを待ちかねて早々に、朝まだ早くに墓に出向いて、せめて香料をお塗りしよう、せめて亡骸を目にして触り、お別れをしたいという気持ちでいっぱいでした。ところが、ご遺体を目にすることができない戸惑いと、打ちのめされた感じで途方に暮れました。
その時、神さまからのお声が聞こえてきました。「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、と言われたではないか。」
これは、最も重要なメッセージであり、またイエス様の生前のお言葉です。彼女らはイエス様の言葉を思い出しました。人はそのお方が語られた数々の言葉を思い出します。その中でも一番強く深く残っている言葉があり、それが宝物です。
14年前の東日本大震災巨大津波によって大勢の方が流されて行方不明になりました。突然、何の前触れもなく身内の身体が取り去られたのです。目の前から消されたのです。愛する人を失った方々は、深い、大きな嘆きを経験しました。時間が空しく過ぎることも経験しました。今日まで、愛する人の魂の平安を祈ることしかできなくそれは、それは長い、長い時間を過ごしておられます。大震災後1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、半年、1年、そして14年が経ちました。
やがて被災者の中には、あの人を決して忘れないこと、世を去られた人のいのちを忘れないこと、そのいのちの分まで大事に生きること、それが遺された者がなすべきことだと考え、自分を納得させる方もおられます。山元町にある、震災で園児と職員を失ったふじ幼稚園園長先生はそう考えて、嘆きを生きる力に変え、回復して前を向いて園を再開し、保育を進めています。
復活とは「そこにとどまらない、そこに縛られない、キリスト・イエスの言葉を思い起こす」ことです。かつてイエス様が約束されたように、復活の主はあなたがたの現実生活の中に必ずや共にいてくださいます。ご復活の主は、いつも共にそして永遠にいてくださいます。「なぜ、生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。」
主イエス様のみ言葉を胸に抱き、ここから歩み出して行きましょう。主にある皆さんとともに新しい朝、復活の朝に目覚めてまいりましょう。栄光に輝くイエスさまの光に照らされて、光を見つめながら導かれてまいりましょう。
教区主教 フランシス 長谷川 清純
「今、ここで、主と共に生きる」2015年7月号
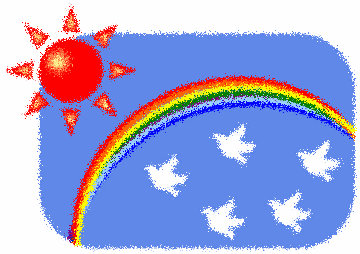 北海道、岩手に次いで、全国で3番目に面積の広い福島県。その広さがもたらしてくれる楽しみの一つに、桜の満開を長く楽しめることがあります。面積の広さに加えて、盆地である福島市は同じ市内でも土地の高低差があり、場所によって桜の満開時季も異なり、したがって、市街地では散り始めていても、少し車を山間部に走らせると、まだまだ満開ということがあるのです。もう桜の季節は終わったと思っていたのに、この辺りの桜は今が見頃なんだ!などという発見があると、うれしい気分になります。今年は、行く先々で満開の桜を見つけるのが楽しみになっていました。
北海道、岩手に次いで、全国で3番目に面積の広い福島県。その広さがもたらしてくれる楽しみの一つに、桜の満開を長く楽しめることがあります。面積の広さに加えて、盆地である福島市は同じ市内でも土地の高低差があり、場所によって桜の満開時季も異なり、したがって、市街地では散り始めていても、少し車を山間部に走らせると、まだまだ満開ということがあるのです。もう桜の季節は終わったと思っていたのに、この辺りの桜は今が見頃なんだ!などという発見があると、うれしい気分になります。今年は、行く先々で満開の桜を見つけるのが楽しみになっていました。
ある日、この日もお訪ねした信徒宅の近くの土手で満開の桜を見つけてしばし鑑賞した後、帰路につくと、今度は、風に煽られて勢いよく散っていく桜の木に出会いました。文字通りの桜吹雪です。みるみるうちに近くの川面が桜色に染まっていきます。それはそれは美しい光景でした。そしてあらためて思わされたのです。私たちは桜を、花が咲き誇っているときだけ愛でてきたのではないことを。
私たちは古来、花びらの舞う光景を“桜吹雪”と呼び、その散った花びらが水面に浮かび流れるのを筏に見立て“花筏”と呼びました。さらに花が散ってしまった桜の木を“葉桜”と呼び、新緑の香りと美しさを愛でました。散りゆく花びらをいつまでも惜しむのではなく、その移ろいを受け入れ、その一瞬一瞬に楽しみを見出してきたのです。それを仮に「受容力」と名付けるなら、桜の木の移ろいのみならず、どんな状況にあっても、それを包み込み、受け入れ、幸せを見出してきた私たちは、そもそも「受容力」の備わった生き物なのかも知れない、そんなことを思いました。
しかし、いつの頃からか、社会には「善悪」「損得」「幸、不幸」「勝ち組、負け組」など多くの二元論が溢れるようになり、今や現代人は相対評価で物事を判断することに慣らされてしまったといえるかも知れません。でも、この世の中が本当に二元論で割り切れるなら、桜の木の折々の状況を受け容れ、愛でることなどできないはず…そう思うのですが如何でしょうか。
弟子たちの主イエスとの一度目の別れ、すなわち受難の前、彼らは、十字架に架けられることなどあってはならないと師をいさめ、さらには師を知らないと拒み、家の戸に鍵をかけていました。そんな弱々しい弟子たちが、二度目の別れ、すなわち主の昇天の際には、「大喜びでエルサレムに帰った」とルカ福音書は記しています(24:52)。弱かった弟子たちが、今度は主との別れを悲しむのではなく喜び、その後も幾多の困難を乗り越えていく力強い宣教者に変えられたのです。この間にあった出来事は主の復活です。彼らは主の復活によって、人間が本来備え持つ「受容力」を呼び覚まされ、強められたのではないでしょうか。
今に生きる私たちも、同じ主の復活を信じて生きる者です。そして、桜の移ろいをどんな時季にも楽しめる「受容力」も与えられています。そうであるならば、課題を数え上げ、自らを取り巻く困難さを声高に主張して、それらすべてを解決しなければ幸せにはなれないと思い込んでうずくまるよりも、今、ここで、主が共におられることに幸せを感じられる一人ひとりでありたいと思います。
被災地にある教区、教会として、聖霊の導きを祈り求めつつ。
司祭 ヨハネ 八木 正言
「日々の中に・・・・」2017年7月号
 朝玄関で「おはようございます!」と声をかけ、小さな声で「おはようございます」と答える子と握手する。午後は卒園児が「ただいま!」と幼稚園にやって来て、「お帰り!」と迎える。これがセントポール幼稚園の毎日で、笑顔溢れる毎日です。
朝玄関で「おはようございます!」と声をかけ、小さな声で「おはようございます」と答える子と握手する。午後は卒園児が「ただいま!」と幼稚園にやって来て、「お帰り!」と迎える。これがセントポール幼稚園の毎日で、笑顔溢れる毎日です。
朝、礼拝堂でのお祈り後、教会の周りを散歩。沢山の出会い――犬を連れて散歩されている方、歩行の訓練をされている方、ごみ収集所でほうきをもって立っている方、お庭のお花にお水をかけている方、学校へと急ぐ学生たち――声をかけ、声をかけられながら。
最近は近くのコンビニの方々から、「今日も早いね、行ってらっしゃい!」と声をかけられる様になりました。秋田出身と伝えたら、「秋田名物八森はたはた~」とレジの前で秋田音頭を歌ってくれました。また、文の最後に「~ばい」を付ける郡山弁を教えて頂いた。「今日は寒いばい!」と慣れない言葉で伝えた時の相手の笑顔が心に残ります。寒い日には「持ってって!」とあったかいコーヒーを渡され、その温もりに「せば、まんず!」と秋田弁で照れ隠しをする自分がいます。
これが日常、郡山での毎日です。日の光を浴び、風を感じ、道端の花を愛でるように、わたしにとっては尊く、何ものにもかえがたい宝物です。
ただ、ただ、毎日を生きる。日々の生活をし、交わり、季節を感じ、それを愛で、感謝し、生きている、いいえ、生かされている。
わたしは、言葉に言い表せない思いで溢れています。心からの感謝と共に、その毎日を笑顔と一緒に大切に歩んでゆきたいと願います。
人は歩みの中で、足りないことや出来ないことを気にしがちです。でも、じっくりとゆっくり見渡せば、既に与えられている恵みが沢山あると思うのです。
自分にないものを考えたらきりがありません。でも、与えられていることに思いを巡らし、感謝し、それから学ぶことの尊さを思います。
わたしがここ、郡山に来た時は緊張・戸惑い・不安で一杯でした。でも、「そのままでいいからね。いてくれるだけでいいんです。」という言葉、体調を崩した自分にご飯を届けてくれた、命の尊さをご自身の想いを短い言葉で伝え励ましてくれた、その一つひとつの温もりが自分に新たな歩みを始めるきっかけをくれました。
私は神様のみ前にいること、教会にいること、そして自分の首にカラーを付けることにおそれを感じます。自分を律し、願い求め、神様の御前に清くありたいと思いながらも、これほど破れがある自分が許せない・・・。それを「そのままで」という言葉が、沢山の想いが、祈りが、そして笑顔が自分を救い、支えてくれています。
多分、聖書の中のみ言葉から皆様にお伝えすることが今回の私に求められていることでしょう。でも、わたしは日々の生活の中に、毎日の営みの中、その只中に、み言葉、そして日々の出会いの中に“主”を感じていることをお伝えしたいと思います。
また明日、礼拝堂でお祈りをお捧げします。教会の周りを散歩します。あのご婦人に会えるかな? あのワンちゃんは元気かな? あのほうきを持って立っているおじさんはいるのでしょうか? 今日は、あの子は泣かないかな? 幼稚園の先生たちは元気かな? 教会に集う皆さんは元気かな? 日曜日のお話し、全身全霊をかけて取り組みます。いつものコンビニでの笑顔と会話、全部楽しみです。
すべてに感謝します、心から。
主に感謝。
執事 アタナシウス 佐々木 康一郎
「バベルの塔再び?」あけぼの2019年6月号
最近「あ、これ欲しいな」と思ってしまったものがありました。「自動翻訳機」というものです。恥ずかしい話ですが、交わりのある海外の教区があるのだから、せめて簡単な会話くらいはできるようになろうと、英語、韓国語学習に挑戦しているのですが、生来の怠け者のせいかちっとも身になりません。そんなところに自動翻訳機の登場ということで仕様を見てみると、何と126もの言語に対応しているとのこと。こんな小さな機械の中に?と驚きましたが、どうやら通信技術を使っているようです。最近よく聞く第5世代・5G通信というものはかなりの高速らしいですから、こういったものが増えていくのでしょう。そして人工知能(AI)が見えない所で活躍しているようです。そういえばAIが進歩するとなくなる職業のひとつに「通訳」を挙げている人がいました。互いに機械に囁きながら会話するという、おかしな場面を想像すると「そんなことないだろう」と思いましたが、ヘッドホン付きマイクで使えるようになれば、普通に会話している感覚になるのかもしれません。そうすると語学学習なんて無駄ということになるのでしょうか。素晴らしいことなのかもしれませんが、何か納得できません。それで本当に意思疎通ができているといえるのか、ということもありますが、言葉に限らず人の交わりが、すべて機械や技術にのみ頼ることになったらどうなるのでしょう。現在個人で手に入るもの、例えば家庭で使用する機器は、故障すれば面倒ですが洗濯や掃除など手動でもどうにかなるもの、しばらく我慢すれば何とかなるものがほどんどです。しかしこれからどんどん技術が進歩して、何も心配しなくてもよい世の中になったと安心した所に、電気も通信も途絶えてしまう大厄難が起こったらどうなるでしょう。さっきまで普通に会話していた隣の人と、突然話が通じなくなります。流通も止まり、日常が崩壊します。旧約聖書のバベルの塔の出来事のようです。どんな混乱が起こるのでしょう。想像もつきませんが、私たちも同じような経験をしています。東日本大震災の時にはすべての生活基盤を突然失い、なすすべをなくした人たちが大勢いたのです。これが地球規模の出来事だったらどうなるのでしょうか。
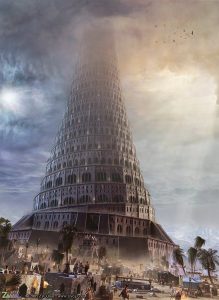 科学の進歩は素晴らしいものです。それは必然でもあります。しかし何か間違えていないのか。人間は神に近づこうというよりも、神を越えてやろうとしていないのか。またもやバベルの塔を積み上げようとしているのではないか、それが高くなればなるほど、すでに神など必要ではないと、思っているのではないかと気にかかります。しかし教会の不振をそのせいにして逃げてはいけないのです。変わりゆく世の中にあって、不変のもの、永遠を告げ知らされた者としての使命は変わらずに、増々重くなっているのではないでしょうか。永遠なるものであるからこそ、福音はどの時代、場所、状況にも適っていくことができることを思い起こしたいと思います。
科学の進歩は素晴らしいものです。それは必然でもあります。しかし何か間違えていないのか。人間は神に近づこうというよりも、神を越えてやろうとしていないのか。またもやバベルの塔を積み上げようとしているのではないか、それが高くなればなるほど、すでに神など必要ではないと、思っているのではないかと気にかかります。しかし教会の不振をそのせいにして逃げてはいけないのです。変わりゆく世の中にあって、不変のもの、永遠を告げ知らされた者としての使命は変わらずに、増々重くなっているのではないでしょうか。永遠なるものであるからこそ、福音はどの時代、場所、状況にも適っていくことができることを思い起こしたいと思います。
私たちは小さな者です。しかし地に蒔かれた一粒の麦は、やがて大きな実りを、命を生み出すこと、取るに足りないように見える一つまみの塩が、地に神の味をつけることができるのです。小さな群れであることを恐れずに、弱いところにこそ働かれる神に信頼し続けたいと思います。
山形聖ヨハネ教会牧師 司祭 ステパノ 涌井 康福
あけぼの2021年2月号
巻頭言「再び会いたいですね」
「教会相互の交わり・協働関係を深めます。」
「教区内17の幼保園(2019年現在)との協働関係を深めます」
これは東北教区宣教方針の2つの柱であるキーワード「ささげる」、「開く」の内の後者の具体的な行動指針として示されているものです。教区宣教方針が2019年11月に開催された第102(定期)教区会で決議されて早くも1年が過ぎました。
昨年はコロナ禍の中にあって教区の諸プログラムのほとんどが中止となりました。今年もどうなるか分かりません。
教会の礼拝は、感染予防をしながら再開されていますが、それ以外の事は自粛せざろうえない状況が1年近く今も続いています。皆さんと一緒に食事をして、語り合ったりする日常が特別な恵みであったことを人の出入りが減ってしまった静かな教会の会館で思います。
 私自身の事を振り返っても教区の諸会議はほとんどインターネットを介したオンラインで参加しています。コロナ前は交通費や時間の節約のためにオンライン会議を教会でも取り入れていければいいなと思っていましたが、結局は話だけで終わっていました。
私自身の事を振り返っても教区の諸会議はほとんどインターネットを介したオンラインで参加しています。コロナ前は交通費や時間の節約のためにオンライン会議を教会でも取り入れていければいいなと思っていましたが、結局は話だけで終わっていました。
しかし、現在ではこれが日常になりつつあります。
オンライン会議はとても便利です。でも何か物足りません。何が物足りないのか。それは相手の感覚です。人間には五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)があります。
人類学者である山極壽一氏が興味深い事を言っています。「人間は、視覚と聴覚を使って他者と会話すると脳で『つながった』と錯覚するらしいが、それだけでは信頼関係までは担保できません。なぜなら人は五感のすべてを使って他者を信頼するようになる生き物だからです。そのとき、鍵になるのが、嗅覚や味覚、触覚といった、本来『共有できない感覚』です。他者の匂い、一緒に食べる食事の味、触れる肌の感覚、こうしたものが他者との関係を築く上で重要」なのだそうです。
コロナが終息するまではなかなか自由に行き来することは難しいと思いますが、いつか必ず皆さんとお会いしたいです。
教会問答の問27に「聖奠および聖奠的諸式、その他教会の働きはだれが行いますか」とあります。答は「神の民(キリストとその教会を表す信徒と聖職)が共同体として行います」です。
これは「教会の働きは一人もしくは各教会単独ではなく一緒に協働していく」ことを示しているだと思います。これは大変重要な事です。
一人の小さな手という歌をご存じでしょうか。「ひとりの小さな手何もできないけど、それでもみんなと手と手を合わせれば何か出来る」
私は教会間協働、幼保園との協働を地道に着実に行っていきたいと思っています。なぜならそれが教会の働きにおいて決定的に大切なことだからです。今は我慢の時です。しかし、私たちがそれぞれの感覚を互いに感じながら再び会える時が必ず来ると信じています。
司祭 ステパノ 越山 哲也(八戸聖ルカ教会 牧師)
あけぼの2023年5月号
巻頭言 東北の信徒への手紙 「さあ、行こう~わたしたちのミッション 主から遣わされている一人として~」
 野球の世界一を決める国別対抗試合WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に夢中になった方も多いと思います。私も無類の野球好きでありまして、WBC開催中は毎日夢中になっていました。試合前に日本代表の選手の一人が声出しをする場面があり、私は試合の内容もさることながら声出しの内容にも夢中になって聴いていました。決勝戦の日、声出しを務めたのは大谷翔平選手でした。第一声は「僕から一個だけ。憧れるのをやめましょう」でした。
野球の世界一を決める国別対抗試合WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に夢中になった方も多いと思います。私も無類の野球好きでありまして、WBC開催中は毎日夢中になっていました。試合前に日本代表の選手の一人が声出しをする場面があり、私は試合の内容もさることながら声出しの内容にも夢中になって聴いていました。決勝戦の日、声出しを務めたのは大谷翔平選手でした。第一声は「僕から一個だけ。憧れるのをやめましょう」でした。
その真意は、「決勝の対戦相手であるアメリカの選手は、野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるようなスーパースターばかりだと思う。僕らは今日超えるために、トップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。」というものでした。
そして決意を込めた表情で「さ、行こう!」と選手全員を鼓舞し、この場に拍手が響きました。大谷選手の言葉によって最高のムードができました。私は大変印象的な場面として心に残りました。そして、選手たちに声出しの最後に決まっていう言葉があることに気付きました。それは「さあ、行こう」です。選手を自らも含めて送り出す最大の力強い励ましの派遣の言葉だと思いました。
教会を意味する「エクレシア」は「主によって集められた民の群れ」という意味があります。そして、宣教とは、主語は「わたし」ではなく神様であって神様が神の国の完成、つまりすべての被造物が真の平和の状態の内に生きることが出来る世界の完成のために働かれている「神の国運動」(ジーザスムーヴメント)に私たちは招かれている。そして神の国は教会という建物の中にあるのではなくこの世界にあるということを主イエスは私たちを「派遣」することで示されました。福音書でも主によって集められた弟子たちを派遣する箇所がいくつも出てきます。「わたしはあなたがたを遣わす。それは、狼の群れに羊を送り込むようなものだ。」(マタイ10:16)
これからあなたがたの人生には苦難が待ち構えているだろう。でも恐れてはいけない。私が必ずあなたと共にいると弟子たちを励まし彼らを送り出しました。その派遣の言葉はご自身にも向けられていたのだと思います。ご自身も幾度となく十字架の苦難の道を歩むことを躊躇され、苦難されている様子が福音書に記されています。
礼拝も主からの招きによってはじまり、「ハレルヤ、主とともに行きましょう」という派遣の言葉によって終わります。
エクレシアは主によって「集められ」、そして「派遣される」民の群れであることを私たちは忘れてはいけないと思います。私たちは新主教を迎えて新たな歩みを始めようとしています。私はワクワクしています。同時に、私たちがそれぞれ置かれている現実の課題や困難にしっかりと向き合い、恵みを発見していきたいと思います。私たちは神の国運動に主から招かれ、そして遣わされているのです。「さあ、行きましょう!!」
主とともに。
盛岡聖公会牧師 司祭 ステパノ 越山 哲也
あけぼの2025年7月号
巻頭言 東北の信徒への手紙 「一歩69cmの繰り返し」
伊野忠敬。江戸時代に徒歩で日本列島を縦断し、日本で最初に実測地図を作った人物です。忠敬は、下総の国(千葉県)佐原にある造り酒屋、伊能家に17歳の時に婿養子に入ります。以来、酒屋の仕事に精を出してきました。婿入り当時、伊能家の家業は危機的な状態にありましたが、忠敬は約10年をかけて経営を立て直し、さらに家業の拡大にも成功しました。当時、忠敬は50歳。
人生50年と言われていた江戸時代。しかし忠敬は何と50歳になってから、小さい頃の夢、天体観測にチャレンジを始めるのです。長男に家督を譲り隠居、天文学を本格的に勉強するために江戸へ出て、浅草にあった星を観測して暦を作る天文方暦局を訪ね、当時の天文学者の第一人者・高橋至時に弟子入りします。このとき師匠の高橋至時は31歳、忠敬は50歳です。当初、高橋至時は、忠敬の入門を”年寄りの道楽”だと思っていましたが、昼夜を問わず猛勉強している忠敬の姿を見て、いつしか至時は弟子の忠敬を「推歩(=星の動きを測ること)先生」と呼ぶようになります。こうして歳の離れた師弟は深い絆で結ばれるようになりました。
 忠敬はなぜ地図を作ろうと思ったのでしょうか。それは、地球の大きさを知りたかったからだと言われています。この初心をもって55歳の時、すなわち1800年4月19日、忠敬は測量の旅に出ます。測量といってもこの時代に機械はありません。人の足と方位磁石を頼りに綿密な海岸線を描いていくという、気の遠くなるような作業が続けられました。3年をかけて北海道、東北、中部地方の測量を終え、江戸に戻った忠敬は、本来の目的であった地球の大きさ計算に取りかかりました。その結果を、後に師匠の至時が入手したオランダの最新天文学書と照らし合わせると、共に約4万キロで数値が一致し、二人は手を取り合って歓喜したといいます。しかもこの時、忠敬が導き出した地球の外周と、現在のGPSとスーパーコンピューターで計算した外周の誤差は、0.1%以下という驚異の精度でした。
忠敬はなぜ地図を作ろうと思ったのでしょうか。それは、地球の大きさを知りたかったからだと言われています。この初心をもって55歳の時、すなわち1800年4月19日、忠敬は測量の旅に出ます。測量といってもこの時代に機械はありません。人の足と方位磁石を頼りに綿密な海岸線を描いていくという、気の遠くなるような作業が続けられました。3年をかけて北海道、東北、中部地方の測量を終え、江戸に戻った忠敬は、本来の目的であった地球の大きさ計算に取りかかりました。その結果を、後に師匠の至時が入手したオランダの最新天文学書と照らし合わせると、共に約4万キロで数値が一致し、二人は手を取り合って歓喜したといいます。しかもこの時、忠敬が導き出した地球の外周と、現在のGPSとスーパーコンピューターで計算した外周の誤差は、0.1%以下という驚異の精度でした。
50歳になっても夢をあきらめなかった伊能忠敬。55歳から17年間、一歩一歩踏み出し続け、地球一周分を歩き抜いた伊能忠敬。考えてみると、彼の人生は、夢に向かって一直線に突き進んだわけではありませんでした。それどころか夢とは何の関係もない、婿入りした先の酒屋の仕事に精を出した人生でした。自分を取り巻く環境を受け入れ、その時にできることを精一杯やり続けたのでした。家族を大切にし、承認として客を大切にしました。彼は直接に売り上げに関係なくても、客のためにできることがあればしてあげたと言います。私財ををなげうって地域の人々を助けたこともありました。そんな彼だったからこそ、夢であった天体観測を超えて、最終的に、夢にすら描いていなかった『大日本沿海輿地全図』の完成という歴史的大偉業へ運ばれたのかもしれません。
忠敬の一歩は69cmであったと言われています。忠敬は計測のため、日本全国を完璧に同じ歩幅で歩き通しました。つまり、右足、左足で足してぴったり138cmで歩く訓練をしたそうです。その執念が正確な地図として実を結んだのでした。
夢に生きるとは、やりたいことだけをやることでも、好きなことだけをやることでもないようです。目の前のことすべてを受け入れ、そのときにできるわずか69cmの一歩を踏み出し続けること…。「神の目は人の道に注がれ/その歩みのすべてをみておられる」(ヨブ記34:21)のです。
仙台基督教会牧師 司祭 ヨハネ 八木 正言
「自分の中の風化」2015年8月号
去る5月30、31の両日に、秋田市で「東北六魂祭」が開かれ、県内外から20数万人の方が秋田を訪れました。予想以上の人出だったようです。東北六魂祭は東日本大震災の犠牲者の鎮魂と被災地の復興を願って、震災発生の年2011年に仙台で1回目が開催されて以来、盛岡、福島、山形と回り、この度の秋田での開催で5回目を迎えました。第1回目の開催の時は仙台におりましたが、翌日の主日礼拝準備が進んでいなかったのでテレビで見ていました。第2~4回もそうでしたが、この度の秋田市開催は会場へ足を運んで見てきました。
大震災以来開催されている東北六魂祭。私も大震災以来続けていることが2つあります。その1つは、毎月11日午後2時46分に東北六魂祭同様、犠牲者の鎮魂と被災地復興を願って教会の鐘を1分間鳴らし、そして主教会作成の「東日本大震災のための祈り」、2014年2月以降から「東日本大震災を覚えて」の祈りをお献げしています。これには北海道在住の親友がその時間帯に共に祈ってくれていることが大きな励ましになっています。彼には大船渡で家業を継ぐ大学時代の友人がおり、その友人の方は直接的な被害はなかったものの、震災以降それまでの生活がガラッと変わり、苦しい状況の中にいるそうで、その方の復興をも願いながら付き合ってくれています。毎月11日の前日または当日に「鐘に合わせて祈るよ」とメールを送ってくれます。彼の後押しが打鐘と祈りを私に続けさせているのだと思います。
もう1つは、20数年続けている私的な「日誌」の当該日の日付の上に、その日が大震災から何日目であるかを記しています。震災発生から4年3カ月を迎えた去る6月11日は1,553日目に当たる日でした。時々震災発生の日に書いたことを読み返すことがあります。読み返しながら当日以降を思い出してみたりしますが、記憶があやふやなことも多々あります。書いてあることが思い出せないのです。これは風化でしょうか。
毎月11日に打鐘と祈りを献げている、と先ほど書きましたが、実を言うと忘れてしまったこともしばしばありました。外出していた時もありました。その日の昼頃までは覚えていても、別なことをしているうちに忘れてしまったことも少なからずありました。ド忘れなのか、それとも「風化」なのかわかりませんが、記憶がだんだん薄れてきていることは確かかもしれません。
そんな中で、先日あるテレビ番組を見ました。ハンセン病問題を特集していた番組で、進行役が実際に「多磨全生園」を訪ね、そこに70年暮らしている方のお話しも放送されました。全国のハンセン病元患者の皆様の願いは「自分たちの存在を知って欲しい」、ということです。この言葉を聞き、私たちの東北教区にもハンセン病で苦しんでこられた方々がいらっしゃることを「改めて」思い起こされました。ここにも私の中に風化が進行していることを認めざるを得ない事実があったことを告白致します。
「霊性」ということの1つの表れとして、祈りの項目(代祷項目)をどれだけ挙げられるかだ、と学んだことを思い出しています。祈りを通して霊性を深め風化を防ぎたいと思います。教区の皆様も祈りのうちに覚えてくださいますようお願い致します。
司祭 アントニオ 影山 博美
「祝福されている私たち」2017年8月号
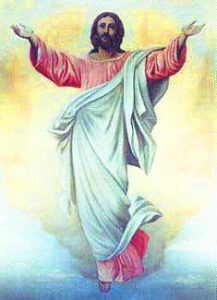 「主教は次の言葉を用いて会衆を祝福する。」と、聖餐式の最後の祝福の祈りの前に小さく記されているのを皆さんは意識されたことがあるでしょうか。
「主教は次の言葉を用いて会衆を祝福する。」と、聖餐式の最後の祝福の祈りの前に小さく記されているのを皆さんは意識されたことがあるでしょうか。
昨年2016年10月に東北教区と親しき交わりにあります米国聖公会ルイジアナ教区主教モーリス・K・トンプソンJr.師父が東北教区を訪問されました。トンプソン主教は限られた滞在期間の中でありながらも仙台基督教会でのメッセージ、講演、そして東日本大震災の被災地も訪問されました。そして10月16日の主日は、八戸聖ルカ教秋宣教120周年記念礼拝にご臨席頂きました。トンプソン主教は、聖餐式の陪餐の時に未信徒の方やまだ堅信を受けていない信徒一人一人の頭に手を置いて祝福をしてくださいました。記念礼拝の後の祝賀会のご挨拶で「今日の礼拝では主教職にとって最も大切なご奉仕をさせて頂く恵みが与えられ感謝します」と述べられました。私は大変印象的なお言葉として心に残りました。また、今年6月11日には加藤博道主教が八戸聖ルカ教会を教区主教として最後の巡回で、聖餐式の司式と説教をしてくださいました。
そして加藤主教も陪餐の時に子どもたちや未信徒の方々に祝福をしてくださいました。
私は両主教が「祝福」をしているお姿にとても感激をしました。礼拝の中における「祝福」という行為は、イエス様からの私たちへの大きな恵みであると心から実感いたしました。皆さんも思い浮かべてください。礼拝や諸行事、会議等で教区主教が臨席されている時は会の最後は主教様の祝福の祈りによって終わることが多いと思います。
主教の祝福に関してのエピソードをいくつか紹介します。
ある主教様は息子さんからの電話があると必ず電話の最後に祝福をしてくださったそうです。またある主教様はご高齢で体のお具合が悪く療養されながら礼拝に出席をされていましたが、祝福の祈りをされる時は、大変力強く張りのあるお声で会衆を祝福されました。またある主教様は病床にあっても看病する家族にベッドから祝福をして下さったというお話しも伺ったことがあります。
主イエス様は復活された後、天に昇られる時に手を上げて祝福されました。そしてこう言われました。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがと共にいる。」(マタイによる福音書28:20)
祝福の祈りを頂くごとに私たちは主の祝福の内に生かされていることを思い出したいと思うのです。喜びの時や嬉しい時だけではなく、むしろ悲しみや辛いとき助けて欲しいときこそ「大丈夫、私があなたと共にいる」という確信を私たちは祝福を頂く事によって得ることが出来るのです。
東北教区が抱える様々な課題、そして皆さんお一人お一人の思いは様々だと思います。しかし、どんな状況であったとしても私たちは祝福され続けていることを覚えましょう。
そして、わたしたちに主の祝福を祈り、私たちの教区を導いてご一緒に共働してくださる次期東北教区主教を選出することが出来ますように、祈り行動して参りましょう。
司祭 ステパノ 越山 哲也

