教区報
教区報「あけぼの」 - メッセージの記事
あけぼの2024年4月号
巻頭言 イースターメッセージ 「復活の主と共に日々を生きる」
以前、新聞の折り込みに「イースターセール」と大書きしたスーパーマーケットのチラシが入ってきたことがあります。日曜日の礼拝後にも話題になり、「テレビのコマーシャルでもイースターセールやってましたよ」と、皆驚いた様子でした。もちろんスーパーが復活日の宣伝をしてくれているわけでなく、クリスマスセールと同様に客寄せのキャッチフレーズだったのでしょうが、思ったほどの効果がなかったのでしょう、翌年には何もなかったと記憶しています。店員さんはお客さんから「イースターって何ですか?」と聞かれて困ったかもしれませんね。それでも「イースターというキリスト教のお祭りがあるんだ」と覚えてくれた人が少しでもいたのならありがたい話ではあります。
 わたしたちはイースターについて、どのように伝えたり、説明したりしているのでしょうか。いろいろな方法があるでしょうが、そこで大切なキーワードは「イエス様のご復活」ということになります。ところが「イエス様のご降誕を祝うのがクリスマスですよ」というと「ああ、それは大事な日ですね」と多くの人が納得してくれるのとは違い、復活というとどうにも反応が微妙です。「はあ、そうなんですね」という言葉の裏には(そんなことあるわけないでしょ)(教会はそんなありもしないことを信じているんだ)という気持ちが透けて見えるような気がしてなりません。だれもが経験したことのないことも、科学的にあり得ないことをすぐに信じることができないのは仕方がありません。完全に命が尽きてしまった存在が再び甦ることはありません。それは常識とか科学とかいう前に、だれもが避けることができない厳然たる事実です。それを打ち破ったのはイエスという方おひとりだけです。そしてそれはキリストを信じる者たちにとって、いつかは死すべきわたしたちも、その復活の命へと招かれるという希望のしるしです。そこにこそキリスト教信仰の神髄があるはずです。そう思いながらも、復活の出来事についていまだにあやふやな自分は何なんだろうと思いめぐらしていると、「待てよ。キリストの目、信仰の目から見たら自分は今生きているといえるのだろうか」という思いが湧いてきました。
わたしたちはイースターについて、どのように伝えたり、説明したりしているのでしょうか。いろいろな方法があるでしょうが、そこで大切なキーワードは「イエス様のご復活」ということになります。ところが「イエス様のご降誕を祝うのがクリスマスですよ」というと「ああ、それは大事な日ですね」と多くの人が納得してくれるのとは違い、復活というとどうにも反応が微妙です。「はあ、そうなんですね」という言葉の裏には(そんなことあるわけないでしょ)(教会はそんなありもしないことを信じているんだ)という気持ちが透けて見えるような気がしてなりません。だれもが経験したことのないことも、科学的にあり得ないことをすぐに信じることができないのは仕方がありません。完全に命が尽きてしまった存在が再び甦ることはありません。それは常識とか科学とかいう前に、だれもが避けることができない厳然たる事実です。それを打ち破ったのはイエスという方おひとりだけです。そしてそれはキリストを信じる者たちにとって、いつかは死すべきわたしたちも、その復活の命へと招かれるという希望のしるしです。そこにこそキリスト教信仰の神髄があるはずです。そう思いながらも、復活の出来事についていまだにあやふやな自分は何なんだろうと思いめぐらしていると、「待てよ。キリストの目、信仰の目から見たら自分は今生きているといえるのだろうか」という思いが湧いてきました。
意識はある。体も動く。それを普通は生きているというのだろうけど、神から与えられた命というものはそれだけのものではないのではないか。そう考えると私だけではなく、たくさんの人が限りある命を精いっぱい生きることができるよう様々な場面で神から力を与えられ、立ち上がらせていただいているのではないか。永遠の命に至る完全な復活とは違うのかもしれないけれど、時には苦しみや悩みで生きながらも死んだようになっていた私たちに、再び希望と力を与えてくださったのはどなただったのか。私たちは今生きている中で、すでに復活の予兆を垣間見ているのではないかと思うのです。キリスト復活の神秘はただ言葉だけでは伝わりません。私たちが経験しているすべての神とのかかわりが、生けるキリストを証しするのです。
当たり前の話ですが、復活祭はその日一日だけのイベントではもちろんありません。私たちの罪の贖いのためその体を死に渡され、更なる希望を示すために復活されたイエス・キリストをほめたたえ、それぞれの日常を復活されたキリストと共に生きるために遣わされていく、それが復活日であり、それに連なる主日なのだと思います。
福島聖ステパノ教会 牧師 司祭 ステパノ 涌井 康福
イースターメッセージ「闇の中で出会う復活の秘義」2015年4月号
主教メッセージからご覧ください。
あけぼの2020年4月号
イースターメッセージ 「不安と疑いの只中で」
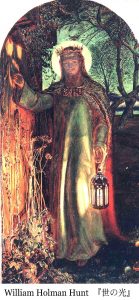 主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。
主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。
その恐れは人間の豹変するありさま、人間のもつ身勝手さに対してであり、人間不信の思いでもありました。しかもそれはユダヤ人に対してだけでなく、イエス様が危機の時、我が身大切のあまり、大事な先生を放り出して蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった、自分自身をも含めた弟子たち一人ひとりに対する不信でもありました。その意味で、彼らは家の扉だけでなく、自分自身の心の扉にもしっかりと鍵をかけ、自分の内側に閉じこもってしまったのです。
このように疑心暗鬼に陥っていた弟子たちの真ん中にイエス様がおいでになって、「あなたがたに平和があるように」とおっしゃっています。普通、私たちはお互いの「不安と疑い」が解消されて後、初めて「主の平和」と言えると思いますが、イエス様は「不安と疑い」の只中に来られ、シャローム、あなたがたに平和があるように」と宣言してくださるのです。
新型コロナウィルスの脅威にさらされている現代社会において、為政者は結果だけを求めているように見えます。結果さえよければ、その過程で起きる不安や疑いは無視されてしまっているように思います。その過程で他の人が苦しもうが、不安になろうが、疑心暗鬼になろうが、全く問題にされません。しかし人間は結果だけで生きているわけではありません。最初から最後までの全ての過程を生きているのです。いやむしろその過程を大切にしながら、苦しみ悩みながら生きているのではないでしょうか。とすればいかに結果がよかろうと、その過程で生じた苦しみや悩み、不安や疑いを帳消しにすることはできないのです。
復活のイエス様は、結果に対して「シャローム」を宣言されるのではなく、その過程の只中においでになり、「あなたがたに平和があるように」と祈ってくださるのです。その過程で生じるありとあらゆる苦しみ、悩み、不安、疑いに対して、「シャローム」と言われ、その只中に生きる私たちの人生を祝福してくださるのです。その只中を生きる私たちと共にいてくださいます。
確かに私たちの人生は、苦しみ、悩み、不安、疑いで満ちています。しかし主が私たちの真ん中に立たれ、私たちと共に歩まれ、「あなたがたに平和があるように」と言われる時、私たちは喜びに満たされるのです。そしてイエス様が「あなたがたを遣わす」と言われる時、あなたは、今あなたが抱えている様々な苦しみや悩みを背負って生きなさい。不安や疑いを持ったあなたそのままの姿で、わたしはあなやをこの世界に派遣する。なぜならあなたは、今のあなたの現実の姿のままで、わたしの「平和」をも携えているからだ。わたしの「平和」を携えている限り、あなたは恐れることはない。
イエス様は、このように私たちに声を掛けてくださっているに違いありません。
教区主教 主教 ヨハネ 吉田雅人
あけぼの2024年5月号
巻頭言 東日本大震災13周年記念の祈り 説教 「いのちの分かち合い」
 2011年3月11日の東日本大震災から13年が経ちました。私はここ福島聖ステパノ教会で祈り、対談する片岡輝美さんから「福島からのメッ
2011年3月11日の東日本大震災から13年が経ちました。私はここ福島聖ステパノ教会で祈り、対談する片岡輝美さんから「福島からのメッ
セージ」を聞いて、原発事故後の現況を知らされて、キリストを信じる者として何かしら行動するようにと促されるでしょう。
毎年何処かで大規模な自然災害が起きる日本で、1月1日能登半島地震に私は震えおののきました。瞬間的に志賀原発はどうなっているか、が頭をよぎりました。大地震と原発事故が絡みます。原発が立つ地域はいわば過疎地であり、同時に大体は震源地近辺ですから、私たちは常時いのちの危険に晒されています。
現在(2月末時点)、能登半島地震の犠牲者は241人、安否不明者も7人にも上ります。2ヵ月経っても1万人以上が避難所生活、4,500人以上が断水状態の自宅避難者です。大きな不安がいつ解消されるのか見通しが全然立っていません。まさに過酷な状況で大変な苦痛と心労を抱えています。
2011年当時、福島県新地町では被災者が仮設住宅に入り始めたのが5月で、どこの被災地よりもいち早く開設されましたが、それでも避難所生活は約3ヵ月にもおよび、大変な心労を抱えたのでした。ですから、能登半島地震で被災された皆さまの一日も早い生活改善がなりますようにとの思いが強まります。神様からのお守りがありますようにお祈りいたします。
「いっしょに歩こう!プロジェクト」の私は、南三陸町志津川に行った折、ある逸話を聞きました。ある小さな村の人々の行動を私は生涯忘れられません。その逸話とは、海岸沿いの被災地から離れた隣り集落代表が、被災し孤立した集落の人たちに、早く食べ物を届けるぞ!と呼びかけ
て、村の方々で握ったおにぎりをリヤカーに積みました。寸断された幹線道路は通行不能で裏の細い山道を行くしかなくても、熱々を食べさせたいと毛布にくるみ決死の覚悟で運ばれました。おにぎりは少し冷めていましたが、大震災翌日、震えていた被災者の口に入って空腹を凌ぎ、人心地と大きな感激の涙と温かな気分に包まれて感謝が伝えられたというものでした。
新地町福田小学校体育館避難所でも、津波が到達しなかった周辺地区住民が、翌日にはおにぎりと味噌汁を漬物と野菜付きで差し入れました。栃木県のアジア学院からは卵や肉を、釜石の小さな漁港の集落に宅配しました。新地町の避難所では久しぶりの肉入りカレーに、本当に美味しかったと人々は満面の笑みでした。つまりは、集められた思いやりの心が人々を満腹にします。寄せ集まった労りの気持ちがささやかで温かな幸せを生みます。
「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」とイエスを試そうとして問うた人は、「あなたはどう思うのか?」と、逆にイエスに問われます。「神を愛し敬い、隣人を自分のように愛すること」答えると、イエスは「正しい答えだ!。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。」と促されます。行いの人にキリストのいのちが宿るのです。
このいのちを分かち合う人になれますようにと、お互いに祈り合ってまいりたいと思います。そのような人を神様はお喜びなさいます。
教区主教 主教 フランシス 長谷川 清純
